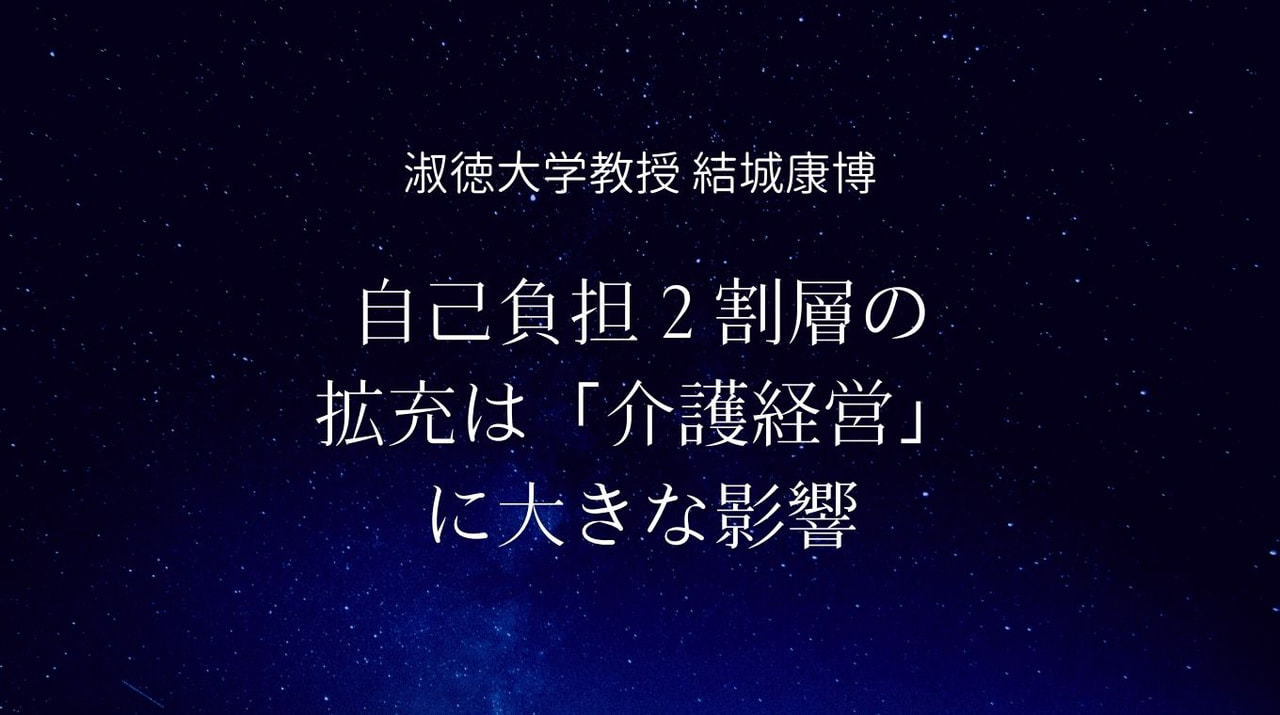2021年6月4日の国会で後期高齢者医療における自己負担2割負担の導入法案が可決した。経過措置があるものの、22年秋から年収約200万円以上が対象だ。また、今年4月、財政制度審議会において24年介護保険法改正において、2割自己負担層の拡充が提案されている。もしかしたら、24年時には一定の高齢者層は医療と介護の自己負担が2割となる可能性も否定できない。本連載の最終回となる今回は、医療と介護の自己負担2割について考えていきたい。
1.高齢者医療2割自己負担の拡充
後期高齢者医療2割自己負担層の拡充で年間約2000億円の医療給付費が抑制できるという。このことで、既存の自己負担3割層と新たな2割負担層を併せると高齢者の約30%が該当することになる。
1人当たりの医療費は高齢になるにつれて増加する。2025年には団塊世代全てが75歳以上となり、急激に医療費が伸びることを見据え、一定の所得のある人には負担してもらうということだろう。
2.24年介護保険法改正への提案
また、4月15日の財政制度審議会資料では「今般の後期高齢者医療における患者負担割合の見直しを踏まえ、介護保険サービスの利用者負担を原則2割とすることや利用者負担2割に向けてその対象範囲の拡大を図ることを検討していく必要」という提案が明記された。
現在の介護保険利用者のうち、自己負担2割及び3割の対象者は約10%が該当し、残りの約90%が1割自己負担となっている(表を参照)。しかし、24年介護保険制度改正において財務省提案が実現し仮に年収200万円以上を2割負担となれば、その対象は3倍にも膨らむことになる。

3.厚生年金受給者も厳しくなる
この約30%層の多くは厚生年金受給者であり、従来、国民年金受給者と比べて老後は安心と考えられてきた。しかし、今後の負担増を考えると、そうともいえなくなる。そもそも年間200万円の年金収入があっても、そこから定期的に上がる介護や医療の保険料が天引きとなり、可処分所得が目減りしていく。
いっぽう年金給付は減ることはあっても増えることはない。そうなると、年金収入を家計の中心に据えている厚生年金受給者にとって、医療と介護が2割自己負担となると厳しい状況になるだろう。
確かに、預貯金を使っていくことも考えられるが、要介護状態となる年齢になると退職金などの蓄えも減少しているだろう。年齢別の要介護認定率は、85歳以上になった段階では、50%を超える(表を参照)。厚生年金受給者であっても85歳や90歳になった段階では預貯金も、かなり目減りしてるのではないだろうか?
かといって娘や息子の仕送りも期待できるか?といったように、高齢者の家計問題を想像するだけでも厳しいに違いない。

4.介護サービスの「利用控え」
このように医療や介護において一定程度の2割自己負担が実現されると、介護サービスにおける「利用控え」が生じることが予想される。特に、在宅介護分野においては顕著に表れると考えられる。
例えば、デイサービスを週3回使っていたのを1回に減らすなど、家計状況に応じてサービス利用量を調整するケースが増えるといった具合だ。訪問介護サービスにおいても同様だ。福祉用具やリハビリ関連のサービスも例外ではない。
自己負担が1割であれば、毎月1.5万円で済んだ負担額が、2割負担になることによって3万円ともなれば、「利用控え」は生じてしまうわけだ。
医療と介護とを比べても「利用控え」の程度については、明らかに介護サービスのほうが顕著となるであろう。医療は利用せざるをえないが、介護サービスの場合は利用者自らが我慢さえすれば、生活自体は維持できるからである。しかも、医師の勧めによる治療に関して患者は同意するしかないが、介護サービスの場合は利用者が受けたいサービス量を主張しやすい。
5.介護経営にも影響が大きい
現在、コロナ禍による「利用控え」は、介護経営に大きな影響を及ぼしている。特に、デイサービスなどはその度合いが大きい。
しかし、24年介護保険法改正によって2割自己負担層の拡充が実現してしまえば、コロナ収束後、これからという時に「利用控え」を引き起こす要素が別の形で生じてしまうことになる。周知のように「訪問介護」「デイサービス」などの事業者は倒産件数も多くこの要因としては、介護人材不足と「利用控え」による影響が大きい。
その意味では、介護保険における2割自己負担層の拡充は介護経営者にとっては、大きな問題でありその動向に注視する必要がある。
6.「混合介護」にも影響
2035年には団塊世代が、すべて85歳となるがこれらの世代は厚生年金受給者層が多い。介護経営者においては、団塊世代を対象に介護保険内・外交えた「混合介護」のビジネス戦略を考えている者も少なくないであろう。
確かに、介護保険内サービスには限界があり、保険外サービスに活路を見出す戦略は正しい。しかし、2割自己負担層の拡充が実現すれば、この戦略も大きく修正せざるをえなくなる。
「混合介護」の主な対象者である厚生年金受給者の家計が厳しくなれば、当然、市場規模は縮小してしまう。現行の有料老人ホーム、サ高住における経営戦略にも大きな影響を及ぼすに違いない。実際、これらの入居系サービスは「混合介護」といった側面が強く、貧困ビジネスを除けば保険外サービスの収入が多くを占めている。やはり、医療と介護の2割自己負担層の拡充は、多くの介護事業所にとって看過できない。
7.社会保険原理にも疑問
本来、普段から病気や介護という事故に備えて保険料を所得層別に負担しているものの、いざ病気となっても同じく窓口負担額が異なるのは、社会保険の原理からすれば筋が違う。高齢化により医療費の財源が必要であれば、さらに保険料徴収時に所得層別に負担を強化させるだけにしておくべきだろう。
不運にも病気となって患者となれば、かなりの高所得層を除いて、一律1割の自己負担割合にしておかないと大半の高齢者は安心した老後を送れないはずだ。
このことを介護現場から発信して、2割自己負担層の拡充は阻止していかないと、結果的には、要介護者の多くが、日常の安心した生活を送ることに対して、困窮することになることが懸念される。