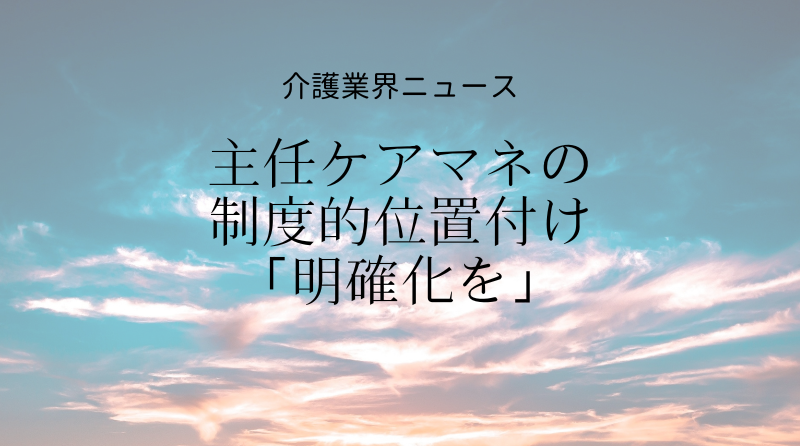ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会では、主任介護支援専門員(主任ケアマネ)の役割についても話し合われました。主任ケアマネには本来、他のケアマネジャー(ケアマネ)への助言や指導を行うことが求められていますが、居宅介護支援事業所(居宅介護支援)、地域包括支援センター(包括)のいずれにおいても人手不足や管理業務などの負担が大きく、求められる役割を担えていないことが課題として認識されてきました。
同検討会は12月半ばにまとめた「中間整理」において、主任ケアマネの制度的な位置付けを国が明確化することや、居宅介護支援と包括のそれぞれの役割に応じた評価の在り方などを検討するよう求めています。
“専門性を発揮できるようにしていくことが重要”
中間整理の記載のうち、主任ケアマネに関する主な内容は以下の通りです。
- 主任ケアマネの役割について、主任介護支援専門員研修実施要綱で、保険医療サービスや福祉サービスの提供者との連絡調整や、他のケアマネに対する助言や指導を行うことなどが定められている
- 居宅介護支援の主任ケアマネは事業所内の介護支援専門員(ケアマネ)への指導者として、また包括の主任ケアマネは包括的・継続的ケアマネジメント支援事業を通じて地域のケアマネへの支援を行う立場として、それぞれの専門性を発揮できるようにすることが重要
- しかし現状では、居宅介護支援の主任ケアマネは事務的な管理業務に時間を費やし、現場のケアマネの指導が十分にできていないといった指摘がある
- 包括の主任ケアマネには、地域包括支援ネットワークの構築を行う役割が期待されているものの、介護予防支援業務や介護予防ケアマネジメントに多くの時間を費やしており、地域の実態把握を行う時間が少ない状況
これらを踏まえ、検討会としては今回、「(主任ケアマネには)地域や居宅介護支援事業所内における比較的経験の浅いケアマネジャーへの指導・育成の役割がある」と明記した上で、国が制度的な位置付けを明確化する検討を行うことが適当だと強調しています。
また居宅介護支援と包括のそれぞれの役割に応じた評価の在り方を検討することも提言しています。
“柔軟な配置”を検討する際は公平性の担保に配慮を
もう一点、中間整理では、居宅介護支援と包括の主任ケアマネの配置についても触れられています。この点については、地域の実情に応じて市町村が役割分担や柔軟な配置(業務委託等)も含めて検討することが適当だとしました。
ただその際は、サービス利用の公平性の担保やケアマネの業務負担に配慮をすることが必要だと加えています。中間整理「案」の時点では盛り込まれた「兼務」の表現は、検討会で慎重な意見が相次いだことを受けて削除されました。


(【画像上】最終的な修正前の「中間整理」案(第4回ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会)の記載より【画像下】正式な「中間整理」の記載より)
検討会での議論 “負担の軽減にはケアプラン件数の抑制が必要”
中間整理の取りまとめまでに6回にわたって開かれた検討会を振り返ると、主任ケアマネを巡っては「業務負担をいかに軽減するか」が中心的なテーマとなってきました。
議論では、スーパービジョンなど本来の役割を遂行するためには、ケアプラン作成に追われる状況を改善しなければならず、担当件数を抑制したり、管理業務を軽減したりする必要があるといった意見が交わされました。
厚労省が示した調査では、居宅介護支援で主任ケアマネの業務に関する課題について尋ねた結果、「業務繁忙のため、主任介護支援専門員に求められる役割に手が回らない」という回答が約6割に上りました。次いで「主任介護支援専門員が担う役割が大きく、燃え尽きてしまう不安がある」が約4割でした。

(【画像】第4回ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会資料より )
構成員からは、一定の担当件数を達成することで支給されるインセンティブが、事業者によっては主任以外のケアマネと同様に設定され、制度の上限いっぱいの件数を受け持つことを求められる点が課題であるとの指摘が出ていました。また、人材育成などに対する明確な報酬設定がない現在の制度上の仕組みについて、「他のケアマネジャーの指導に要する時間等も踏まえて評価をすることが必要」といった提案も出されました。
包括では介護予防支援業務の負担軽減が論点に
地域包括支援センターにおいては、主任ケアマネの介護予防ケアマネジメントの負担をどう軽減するかが課題となっています。介護予防支援の指定対象が居宅介護支援事業所にも拡大されましたが、介護予防ケアプランの報酬が低いことなどから、事業所が積極的に引き受ける流れには至っていません。
このような状況に対し、担い手を増やすため構成員からは、更新をしていない潜在的な介護支援専門員に一定の研修を受けてもらい、予防プランナーとして就労する仕組みを作ってはどうかといった提案が上がりました。
近年、生活課題が複雑化する中で、地域全体の体制整備を進めたり、困難事例を抱えるケアマネを支援したりすることには大きな意義があります。こうした業務に重きを置けるよう、包括の主任ケアマネの負担軽減は重要な課題として、これからの法改正を巡る検討でも位置付けられることになりそうです。