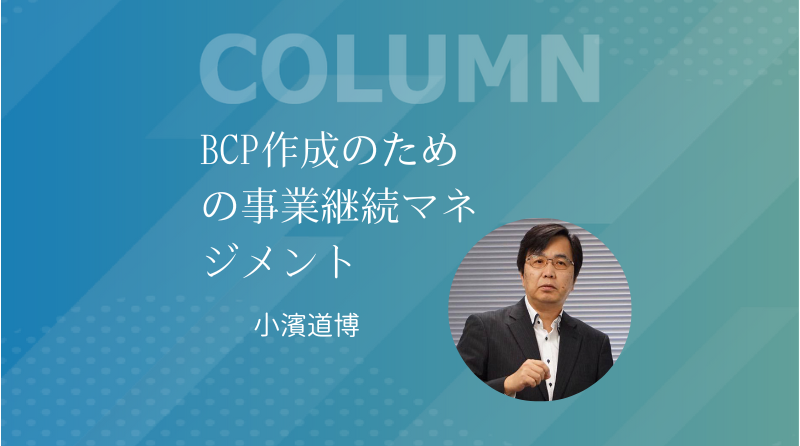迫る首都直下型と南海トラフ地震
内閣府の資料によると、首都直下型地震では、最大震度が7となる地域があるほか、広い地域で震度6強から6弱の強い揺れになると想定されている。最大で死者が約2.3万人、建物の全壊及び焼失棟数が約61万棟、経済被害は、建物等の直接被害だけで約47兆円である。南海トラフ地震では、静岡県から宮崎県にかけての一部では震度7となる可能性があるほか、それに隣接する周辺の広い地域では震度6強から6弱の強い揺れになると想定されている。関東地方から九州地方にかけての太平洋沿岸の広い地域に10mを超える大津波の襲来が想定されている。最大で死者が約32.3万人、建物の全壊及び焼失棟数が約238.6万棟と想定されている。被災地の経済被害は最大で約169.5兆円である。
介護事業者に災害時における業務継続への取り組みが求められているのも必然といえる。
介護事業におけるBCP策定のハードル
BCPとは、地震や台風などの自然災害やコロナのような感染症によって、電力・ガス・水道・インターネット等のインフラ環境や介護施設・事業所の設備が損傷することになり、出勤出来る職員が不足しても、早期に介護サービスを再開ができるように、事前に被災時の対策をまとめた計画書やマニュアルを指す。
ただし、介護・福祉のBCP作成には独特の手順が必要になる。2021年度の介護報酬改定でのBCP策定義務化に伴い、厚生労働省は独自の様式を示している。
この様式に沿ってBCPを作成する場合、介護事業の諸法令や基準、Q&A、特に災害時の制度上の特例措置に、ある程度精通していることが求められる。感染症対策下でのサービスの継続など一般企業には無い要素も多く盛り込む。通所サービスに至っては、休業という要素を盛り込まないといけない。
さらに、惨事ストレス対策などのメンタルケアの要素も必要になるために、介護事業のBCP策定のハードルはかなり高く、インターネット等から得た手軽な作成事例をコピペして作成出来るものではない。地域や施設によって自然災害や感染症のリスクは異なるし、併設している介護サービスも違う。介護サービスに対する基本的な考え方(基本理念、クレドなど)も各々の介護事業所で異なる。そのため、事業者毎にオーダーメイドでの作成が求められる。
また、BCPは管理者が一人で作り込むものではないという認識が必要だ。BCPの策定は、現状の仕組みや運営手順を計画のフォーマットに落としこめば済むものではなく、施設や事業所の現状の問題点を把握して、その解決策を皆で検討しながらBCPを作り込んでいくものだからである。
事業継続マネジメント(BCM)の考え方を理解した効果的・効率的なBCPの策定
BCP作成の全体像を理解するために、中小企業庁のBCPで取り入れられている事業継続マネジメント(BCM)の考え方が参考にできる。
全体像やゴールを把握し、メンバー間で共有できていないままBCPの作成を進めると、途中で道に迷ってしまい、策定に膨大な時間がかかるだけでなく結果的に挫折するケースが多いようである。
このマネジメントサイクルをしっかりと共有してから作成をスタートしよう。
BCP作成の第一歩は、BCP作成委員会の立ち上げから始まる。委員会は、各拠点でサービス毎の責任者、管理者で構成される。そして、介護事業所に必要な取り組みはBCPの作成だけではない。その後、定期的な研修と訓練を実施する必要がある。そして、それに基づくBCPの見直しが重要だ。そのプロセスを確認していこう。
【1】事業を理解する
介護事業所におけるBCPは基本的に、厚労省が用意したひな型の順に作成を進める。項目毎に自施設・事業所の現状を確認して、問題点をピックアップする。ここで、見出しに挙げた「事業を理解する」とは、介護事業所・施設をアセスメントして分析する作業を言う。そして、感染症や自然災害に被災したときの状況について、職員の出勤率などパターンを幾つか想定し、継続する介護サービスの優先順位を被害状況に応じて決める。また、サービスの継続を最優先に置きつつも、出勤率やライフラインの状況に応じて、提供出来る業務と、提供が難しい業務を事前に想定する。
ここまではサービス継続の在り方全体について考え方を論じてきた。
計画表に記載する個別項目についても、分析して理解するステップが必要になる。例えば「非常食や衛生用品の備蓄」という項目であれば、現在の備蓄品を棚卸して一覧表を作成し、その品目毎に作成委員会で備蓄する品目や量を検討するなど作業を進めるといったイメージだ。
【2】BCPの準備、事前対策を検討する。
このプロセスでは、【1】でピックアップした問題点に対する、事前準備や対策を検討していく。例えば、先の備蓄品という項目であれば、その備蓄量の根拠の確認と修正の必要の有無の確認を行う。不足すると判断した品目は購入しておく。また、保管場所が適切かどうかも検討する。重量にある水のペットボトルなどを一階の倉庫に保管していた場合に、浸水被害が起こったときにどうするか。停電が発生してエレベータが使えないとき、少ない出勤者で、3階や4階と言った高層階にどうやって移動させるか等を、実際に被害が起こったことを想定して検討していく。そのような状況を想定して、検討した結果として、高層階については、事前に各部屋にペットボトルを2本配付しておく等の事前対策を考える。このプロセスでは、テーマによっては、委員が各拠点に持ち帰って、一般職を含めての検討も必要になる。
【3】BCPを策定する。
【2】でまとまった事前対策や被災時の対応策をBCPに書き込む。厚労省のひな型の項目に沿って、【1】から【3】のプロセスを繰り返し実行する。また、BCPを発動する基準を設定して、役割分担を明確にする。職員の参集基準や地域との連携方法も検討しなければならない。それらを厚労省のひな型に書き込んで文章化していく。繰り返しになるが、BCPの作成プロセスとは、現状を分析して、「対策」を検討した結果をまとめる作業である。だからこそ、一人に任せるのではなく組織で取り組む必要がある。完成したBCPを机の引出に入れて、その後、何年も日の目を見ることが無いようでは、全く意味がない。次のプロセスが待っている。
【4】BCPの文化を定着させる。
作成したBCPは、非常時に発動して速やかな対策を実施するためにある。そのためには、BCPにまとめた内容を全ての職員の身体に染みこませておくことが必要である。そのために、定期的な研修と訓練を実施する。厚労省の通知では、介護施設は年2回、在宅サービスは年1回とされている。これを繰り返し、繰り返し、全職員で実施することで組織にBCPが定着する。
【5】BCPの維持、更新を行う。
研修と訓練を実施すると、「これはちょっと違う」「もっと良い方法がある」というように頭の中で考えた対策や方法とのギャップが出てくる。BCPに定めた内容を、実際に訓練で実施してみると中々スムーズな対応が出来ないという問題に直面するだろう。そこで明らかになった課題に対応できるよう何度もBCPを書き換えて、試行錯誤を加える。BCPは研修と訓練を終える度に見直し作業を行っていく。そして、見直しの度に最初に戻る。これが、BCMのマネジメントサイクルの考え方である。

訪問サービス、通所サービスの固有事項
訪問サービスのBCPについては、被災時に利用者の居宅での対応、避難所でのサービス提供、有資格者が不足して十分な職員が確保出来ない場合の対応などを盛り込む必要がある。また、感染症では感染者が自宅療養している場合、訪問サービス提供の担当者の選別基準、自宅から直行直帰の場合の連絡方法、利用者自宅でのゾーニングの方法等も定めておく。
通所サービスでは、サービス提供時に被災して、利用者が帰宅できない場合の対応などを検討する。状況によっては、事業所に宿泊するケースも想定しなければならない。その場合の、備蓄品なども検討が必要だ。またやむを得ずに休業する場合、代わりの訪問事業者に引き継ぐなどの対応策を、事前に居宅介護支援と検討しておく必要がある。