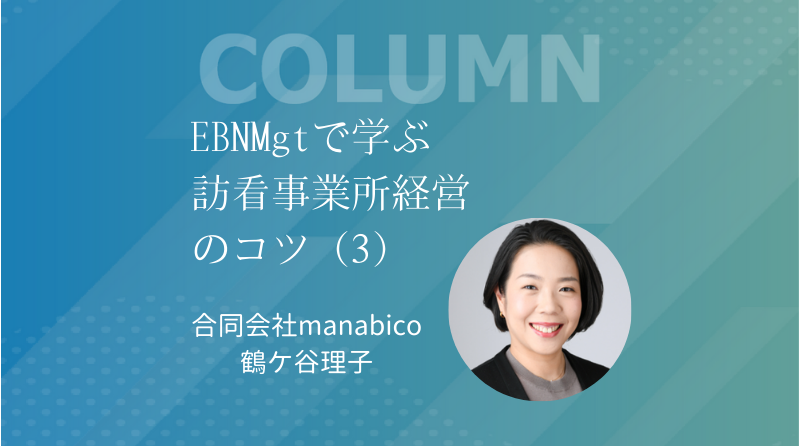はじめに―訪問看護ステーションの離職率を下げるには
訪問看護ステーションの管理者や経営者にとって一番避けたいことは何か尋ねると、スタッフの離職という意見は必ず出てくるのではないかと思います。
全国の訪問看護師の離職率を調査したデータはありませんが、例えば神奈川県が2021年10月に実施した「令和2(2020)年度 看護職員就業実態調査結果(訪問看護ステーション)」によれば、神奈川県の訪問看護ステーションにおける看護師の離職率は18.5%となっています。
離職率を下げ、安定したサービスを提供していくためにも、そして事業所の経営を安定させるためにもスタッフのリテンション(人材の維持・確保)は訪問看護ステーションの管理者・経営者にとって最も大切な仕事の一つです。
リテンションを行うために管理者は、スタッフの仕事に対するモチベーションを高め、活き活きと仕事に向かってもらわなくてはなりません。
ではどうすればスタッフのモチベーションを高めることができるのでしょうか。
モチベーションについては多くの研究が行われており、様々な知見が蓄積されています。その中でも現場の管理者の方に扱いやすい理論として、モチベーション理論の古典であるハーズバーグの二要因理論をご紹介します。
とてもシンプルな理論で、この記事をお読みになった後からすぐに使うことができます。
今日から使えるスタッフの動機づけ~理論の古典:二要因理論~
二要因理論(別名は動機づけ衛生理論)は、アメリカの心理学者であるフレディリック・ハーズバーズが1959年に発表した「The Motivation to Work(邦題『仕事と人間性』北野利信訳)」で提唱した理論です。
この理論では、満足と不満足の度合いを単一のスケール上で測るのではなく、「満足」と「不満足」はそれぞれが独立して作用すると考えます。
つまり、仕事に対する満足感の要因は、仕事に対する不満足感の要因とは別のものなので、別々に考える必要があるということを示しています。

より端的に言えば、満足をもたらす動機づけを行なっていても、不満足をもたらす衛生要因を減らさなければ、離職への可能性が高まる。
つまり、管理者がスタッフに対して満足への動機づけを行ったとしても、スタッフの不満足の要因を消すことはできないのです。
訪問看護ステーションで看護師が辞める理由
この二要因理論から考えてみると離職理由には、職務満足をもたらす動機づけ要因がないので辞める、もしくは職務不満足をもたらす衛生要因があるので辞める、という2つのパターンがあるとわかります。
弊社がこれまで幾つかの事業所を見てきた経験から言うと、訪問看護ステーションにおいては、職務不満足を減らす取り組みというものが足りずに看護師の離職に繋がっていることが多い印象です。
職務不満足をもたらす要因としては、給与・会社方針・人間関係などがあります。これらの要因がスタッフの職務不満足をもたらさないようになっているかどうか、一度確認してみるのもよいのではないでしょうか。
実際の離職理由はもっと複雑でしょうが、離職を避け、スタッフに活き活きと仕事に取り組んでもらうために管理者はどのように働きかければよいかを考える時、二要因理論は指針を明確に与えてくれます。スタッフの動機づけを高めるのか、それとも不満足の要因を減らす取り組みをするのか、という2つの方向性です。
訪問看護管理者は2つの面からスタッフの動機づけを行う必要がある
訪問看護の仕事では、看護師は利用者の居宅に訪問して看護を提供します。訪問は1人で行うことがほとんどなので、仕事のやりがい=職務満足は主に利用者やその周囲にいる人たちから得ていると考えることができます。
そこで、管理者はスタッフ自身の職務不満足を減らすような支援をすることが大切です。
例えば、現場での仕事の不安を解消するために小まめに状況を確認してスタッフがその利用者を看護することについて不安を抱いているのであればその不安を解消する支援を行い、あるいは経験の浅い看護師であれば見過ごしがちな利用者の変化を感じ取れるようにする働きかけをする。または、ステーションとしての訪問看護の方針について説明して訪問看護の現場で行う以外の営業や書類仕事等の必要性について理解してもらう、といったアプローチで職務不満足を減らすことができます。もちろん、できる限りシフトの希望を叶えるという姿勢を示すことも重要です。

弊社の経験からも、経営的に安定し、スタッフが活き活きと活躍している事業所では、管理者がこの2つの面を考慮してスタッフに働きかけを行なっていることが多いと言えます。
次回は、二要因理論の活用方法について具体的な事例を用いて解説します。
参考文献
神奈川ホームページ『令和2(2020)年度看護職員就業実態調査結果(訪問看護ステーション)』 (最終アクセス確認日:2022年2月18日)
ハーズバーグ F著 DHBR編集部訳(2003)「二要因理論:人間には2種類の欲求がある モチベーションとは何か」『DHBR』,2003年4月号,44−58頁,ダイヤモンド社
スチュアート・クレイナー著 嶋口充輝監訳 岸本義之・黒岩健一郎訳(2000)『マネジメントの世紀 1901~2000』139-149頁,東洋経済新報社
スティーブン P. ロビンス著 髙木晴夫訳(2009)『【新版】組織行動のマネジメント』,78-86頁,ダイヤモンド社