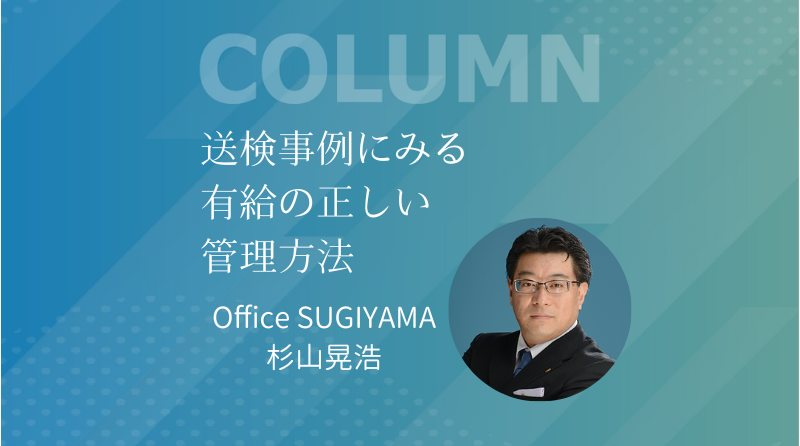違法な残業によって関連する経営者が書類送検される事例はよく耳にしますが、年次有給休暇にまつわる書類送検はそうそう耳にしません。でも、最近は増えてきているんです。そのきっかけは、働き方改革です。どのような事例が書類送検となっているのか、具体例と事業所で取り入れられる改善のポイントを紹介します。
1.働き方改革における年次有給休暇の取扱いの変化
「働き方改革関連法」は2019年4月1日から順次施行されています。
その中でも最も重要視されているのが、「時間外労働の上限規制」です。
2019年3月31日までは、残業をいくらさせても、時間外労働割増賃金を支払っていれば何らおとがめはありませんでした。ところが、4月1日以降は、罰則(6カ⽉以下の懲役または30万円以下の罰⾦)が適用されるため、残業削減に必死に取り組む中小企業が増えました。
一連の改革のもう一つの目玉が、「年次有給休暇の取得義務化」です。
2019年4月1日から全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち利用日数が年5日に満たない労働者については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。
もともと年次有給休暇を利用するためのルールは、「労働者自らが申し出ること」でした。しかしながら、年次有給休暇の利用を申し出る行為自体がし難いというのが日本企業の現状でした。下記のグラフを見てみると、長らく低迷していた労働者1人平均有給休暇取得率は、働き方改革関連法の施行を機に、急激な上昇傾向となりました。

(【画像】厚生労働省「年次有給休暇の現状について」より抜粋)
なお、年次有給休暇にまつわる罰則は以下のとおりとされています。
| 違反内容 | 罰則内容 |
| 年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合 | 30万円以下の罰金 |
| 使用者による時季指定を行う場合において、就業規則に記載していない場合 | 30万円以下の罰金 |
| 労働者の請求する時季に所定の年次有給休暇を与えなかった場合 | 6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金 |
罰則について重要なことは、「罰則による違反は、対象となる労働者1人につき1罪として取り扱われること」です。
例えば、10人の労働者に年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合の罰金刑の最大額は以下のようになります。
10人 30万円 = 300万円
スタッフ数の多い介護事業所が上記の罰金刑を受けると、かなりの痛手になります。
しかし、次のような考え方をする中小事業主も多かったのではないのでしょうか。
「ただでさえ人手不足でシフトが回らないのに、これ以上休まれたら業務が回らなくなる」
「法律改正されたからといって、いきなり罰則を下されることはないだろう」
「残業は個人の問題だが、年次有給休暇は事業所全体の問題だから、年休5日取得義務を履行できなくてもスタッフはみんな理解してくれるはず」
確かに施行初年度は、いきなり罰則を加えられることはありません。厚生労働省のパンフレットには「労働基準監督署の監督指導においては、原則としてその是正に向けて丁寧に指導し、改善を図っていただくこととしています」と記載されています。
これが、「年休5日取得義務の履行は、後回しにしよう」と考える中小事業主を生み出すことになったのかもしれません。でも、あっという間に月日は経ってしまいます。そして、年次有給休暇にまつわる書類送検の事例が増えてきているのが現実なのです。
2.年休の時季指定を怠り送検された事例と改善のポイント
ここからは、具体的な送検の事例を見ていきましょう。まずは、茨城県の龍ヶ崎労働基準監督署が、年10日以上の年休が付与される労働者全員に対して時季指定を怠り、年5日間を取得させていなかったとして、会社と代表者を送検した事例です。
【事例の概要】
本事案は、労働者からの申告が端緒となって発覚しました。
申告に基づき、労働基準監督官が調査し、その結果「パートタイム労働者を含む60人以上の労働者がいたが、そのうち年休の日数が年10日以上の労働者全員について、年休の時季指定を怠り、年5日間を取得させていなかった」ことが判明しました。
労働基準監督官が、会社に是正勧告を行うも、改善の意思が見られなかったため、会社と代表取締役が送検されました。
さらに、「パートタイムの労働者2人が退職前の2カ月間に申請・取得した年休について、賃金の一部を支払わなかった」疑いでも送検されました。
会社の言い分としては、経営不振だから年休を与えられなかったとしています。実態として、労働者から年休の申請があった際も、ほとんどの場合は取得を認めず、欠勤扱いとしており、年休の取得状況は年間で1〜2人の労働者が1日取得する程度だったようです。
【改善のポイント】
⓵年次有給休暇は一定の条件を満たせば全ての労働者に付与される
年次有給休暇は、次の(a)(b)2つの付与条件を満たせば全ての労働者に与えられます。
(a)雇い入れの日から6カ月経過していること
(b)その期間の全労働日の8割以上出勤したこと
なお、この6カ月間には試用期間を含みます。遅刻、早退の場合でも出勤とされます。年次有給休暇を利用している日などは、出勤したものとして取り扱われます。
②パートタイマーでも10日以上年次有給休暇が発生することがある(比例付与)
出勤日数の少ないパートタイマーであっても、年次有給休暇は発生します。下の表を参考にして就業規則整備、代表者を含む組織内のすべてのスタッフとの共有しておきましょう。
なお、年次有給休暇を利用申請する際の手続きなど、組織内でルールを確立しておく必要があります。


(【画像】厚生労働省ウェブサイトより抜粋)
3.年休5日の義務を履行できていると虚偽陳述したために送検された事例と改善ポイント
こちらは福岡県の久留米労働基準監督署が、労働基準監督官に対し虚偽の陳述を行ったとして、会社と担当課長を送検した事例です。
【事例概要】
本事案は、労働基準監督官が事業所に直接訪問する臨検の際に発覚しました。
臨検で年休の取得状況が分かる書類の提出を求めるも、有給休暇管理簿が出てきたのは約1カ月後だったようです。
提出された有給休暇管理簿には、「全員取得した」という虚偽の内容を記載してあり、提出の際には口頭で虚偽の説明が行われました。労働基準監督官は、出勤簿などから、実際は複数人の労働者が取得していない事実を確認しています。1日も休んでいない者もいたという状況でした。
送検容疑は虚偽陳述のみでした。なお、年次有給休暇取得義務違反については行政指導で改善を求めています。
労働基準監督官は、「年休取得は義務化されてから日も浅く、正直に報告してもらえれば、1回目でただちに司法処分にはしない。まずは是正勧告で改善を求める」と話す一方で、「嘘をつかれると、その後の報告が信用できなくなる。虚偽陳述は悪質と判断し司法処分せざるを得ない」としています。
【改善のポイント】
⓵嘘をつかない
法令違反を隠すために、事実と異なる書類を作成・提出しようとする実務担当者の心理は理解できます。労務管理ができていなかった責任を社内的に追及されたくないのでしょう。
でも、虚偽報告はいけません。助成金申請の際に事実と異なる書類を提出するなどすれば、詐欺罪として逮捕されます。
本事案では、代表者ではなく、担当課長が送検されています。従業員の身分で送検されてしまうと将来の昇進、昇格にも影響が少なくないと考えます。
②必要な書類は常日頃から整備しておく
有給休暇管理簿がなければ、誰がどれだけ年次有給休暇の権利を持ち、どれほど利用しているのかわかりません。多くの企業では、部門責任者、人事担当者などが、年次有給休暇管理簿を利用して、年間5日取得義務の履行に気を遣っています。
最近では、勤怠管理システムに年次有給休暇管理システムが連動しているものを導入している企業が増えています。中には、あらかじめ設定しておくことで、年休5日取得を促すアラートを発するものもあります。
勤怠管理システムを利用するときは、システムごとに癖があるので、デジタルアレルギーがあるような人事担当者であれば、アナログ式の年次有給休暇管理簿の活用をお勧めします。
※今回の記事の最後で【年5日取得義務を忘れない「年次有給休暇管理簿」】を希望者全員にプレゼントします。
4.年休取得申請に応じず送検された事例と改善ポイント
最期に、愛知県の津島労働基準監督署が、年次有給休暇取得の時季指定を怠ったとして、会社と各事業場の責任者である店長3人を送検した事例を取り上げます。
【事例概要】
本事案は、労働者からの相談に関連し、労働基準監督署が捜査をする中で発覚しました。
会社は、年次有給休暇が10日以上付与されている労働者 6人に対して、時季指定を怠ったまま1日も取得させていませんでした。6人のなかには、短時間労働者であるパート・アルバイトの従業員も含まれています。
各事業場の労務管理は店長が担っていましたが、従業員が休むと自身が代理で出勤しなければならないため、年休取得の申請に応じていなかったようです。複数の事業場で過半数の労働者に5日分の年休を取得させていませんでした。今回は、労働者数が10人以上の3事業場の店長のみ、取得調整が十分可能であったとして、送検対象とされました。
なお、営業職は自己申告による勤怠管理をしていますが、社外での業務中の勤務実態が明確でないとして、会社は賃金を支払っていませんでした。社内で書類作成に当たるなど勤務実態が明確な時間への賃金も支払わなかったこともあるようです。その結果、賃金未払いや最低賃金法違反でも送検されています。
【改善のポイント】
⓵管理職教育を行う
店長が自分本位の考えにより、従業員からの年休取得に応じていなかったことが大きな問題です。
一般的には、管理職が勤務シフトを作成することが多いのではないでしょうか。介護事業所の人事担当者から『勤務シフト作成者が、自分や関係が良好なスタッフの希望を先に聞いてシフトを組んでいるようだ。どうしたらこの状況を改善できるのか教えて欲しい。』と相談を受けることがあります。
このようなときには、労働法の基本とマネジメント業務を理解してもらうための管理職研修をおすすめしています。
②従業員間のコミュニケーションを改善する
『自分さえよければそれでよい。』と考える自己中心なスタッフや『年次有給休暇は自分の権利だからいつ使おうともかまわない。』と考える権利意識の強いスタッフがいると組織内がギスギスしてきます。最悪の場合、優秀なスタッフが退職してしまうことになりかねません。実際に、このような相談事例を数多く受けています。
年次有給休暇の利用に関しては、会社は時季変更権を行使できますが、法律論だけではこのような環境は改善しません。
全てのスタッフが希望するときに年次有給休暇を利用できるようになるためにはどのようなことが必要なのかをスタッフ自身が考えるような研修が有効です。
さらに協調性をたかめるために、選択理論をベースにしたコミュニケーション研修などもお勧めします。
◆年5日取得義務を忘れない「年次有給休暇管理簿」のプレゼント◆
最後までお読みいただきありがとうございます。
今回は、【年5日取得義務を忘れない「年次有給休暇管理簿」】を希望者全員に無料プレゼントします。自社の組織に合うように、カスタマイズしてご利用ください。
お気軽に下記からお申し込みください。
年5日取得義務を忘れない「年次有給休暇管理簿」プレゼント希望