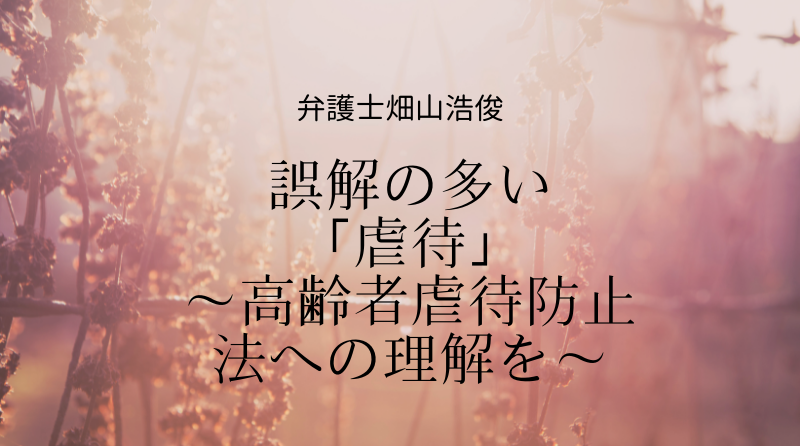(※)高齢者虐待防止法の正式名称は、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」です。本稿では、便宜上「高齢者虐待防止法」という略称を用いております。
1.「虐待」と聞くと何をイメージしますか?
とある特別養護老人ホームでの出来事。
花子(仮名)は80歳、要介護5で寝たきりであり、全面的な介助が必要な利用者であった。
ある朝、看護師の職員が出勤し、花子の様子を見にいったところ、花子の顔面が大きく腫れあがった状態で発見された。
一体何があったのか。
当時、夜勤を担当していたのは1名の介護職員。
花子は、発見当時、顔面が腫れ上がった状態でベッドに仰向けになっていた。
この事態に驚いた看護師は、急いで救急車を手配した。
搬送先の医師は、花子の顔面の怪我の状態を診察したが、その他にも体に多数の痣があることを発見した。
MRIを実施すると、慢性硬膜下血腫であることも判明。
医師はこれらの所見を踏まえ、虐待の可能性があると判断し、行政に通報。
何故このような事態が発生したのか、介護施設で調査を開始した。
当然のことながら、夜勤を担当していた介護職員が何らかの関与をしていると思われたので、詳しくヒアリングした。
結果、介護職員が不適切なケアをしたことから介護事故が発生したことが判明した。
花子は寝たきりで、ひとりで端坐位を維持する事が困難であったにも関わらず、夜勤担当の職員が朝6時頃、ベッドに座らせ、数十秒、その場を離れたというのだ。
円背で端坐位ができないことから、前のめりに倒れてしまい、そのまま花子は床に顔面を打ち付けたと考えられる。
さらに、このヒアリングの中で、かねてからの人出不足で、花子を介助する際、複数の職員で対応しなければならないところ、1名のスタッフでケアすることが常態化しており、それが原因で、体をベッド柵に打ち付けたり、頭をぶつけたりしてしまうことが頻繁に生じていたことも併せて発覚した。
介護施設側は、重大な過失があると考え、すぐにご家族に謝罪対応し、不適切なケアをしたことを謝罪した。
しかしながら、この事故から3カ月後、行政から、この事故は、高齢者虐待防止法の「身体的虐待」「介護・世話の放棄・放任」に該当すると伝達され、調査が入ることになった。
介護施設としては、夜勤の介護職員は確かに不適切な介護を行ったものの、わざと花子の顔面を殴打した訳では無い。また、関わった他の職員もわざと暴行を加えたことは無く、人出不足が原因で、結果として満足なケアができず、花子の体に痣ができたり、頭をぶつけてしまったりしたのだ。
何故これが「身体的虐待」「介護・世話の放棄・放任」と言われるのか、行政の判断に納得がいかない。この調査は受けるべきなのか、それとも徹底的に抗議すべきなのだろうか。果たして、この介護事故は「身体的虐待」「介護・世話の放棄・放任」に該当するのだろうか。
この事例は、実際に発生した介護事故事例を、筆者が一部アレンジしたものです。
皆様は、「虐待」という言葉を聞くと、何をイメージしますか。
この問いに対して、直感的にどのような場面が思い浮かぶか。
これが、この事例を考える上で大切なポイントです。
インターネットで「高齢者虐待 事件」と検索すると、「入所者の首を絞めて殺害」、「介護施設の高齢者殴りあばら骨折させた疑い」、「一晩で40回以上、殴る蹴るを繰り返し」という、ショッキングな見出しの記事が目に飛び込んできます。
皆様も高齢者虐待に関する報道に触れる際、「暴行を加える」「2階から投げ落とす」などの暴力を伴った表現を耳にしたことがあるのではないでしょうか。
このように「虐待」という言葉自体のイメージや、報道などで植え付けられるイメージから、「虐待」とは、「わざと高齢者に暴行を加える行為である」という故意の言動を指すのであって、過失は含まれないのだ、と何となく理解している人がいます。しかしながら、これは大きな誤解です。
2.「刑法」と「高齢者虐待防止法」の違い
「虐待」とは「わざと高齢者に暴行を加える行為」だと考えてしまう理由は、報道で取り上げられる「虐待」行為が、「刑法」上の故意犯に該当するものばかりだからです。
例えば、わざと人を殴る行為は、刑法上、暴行罪(刑法208条)に該当しますし、殴った結果、あばら骨が折れるなどの怪我を負わせると、傷害罪(刑法204条)が成立します。
さらに、あばら骨が折れ、結果的に死亡すると、傷害致死罪(刑法205条)になりますし、仮に、「殺してやる」「死んでも構わない」と思って、首を絞めたり、2階から利用者を投げ落したりして、結果的に死亡した場合は、殺人罪(刑法199条)が成立します。
報道される「虐待」行為は、このような「わざと」行った犯罪行為が大半であり、そのため、報道を見ている側としても、このようなイメージが定着してしまっているのです。
しかしながら、高齢者虐待防止法が定める「虐待」の定義は、刑法上の故意犯とは別物です。
行政は、この事例における職員の行為について、「身体的虐待」と「介護・世話の放棄・放任」に該当すると認定しています。
高齢者虐待防止法では、介護職員に関する「身体的虐待」について、「高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること」と規定しています(同法第2条5項1号イ及び2号)。
また、「介護・世話の放棄・放任」について、「高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること」と規定しています(同法第2条5項1号ロ及び2号)。
重要なポイントは、これらに該当するかどうかは、携わった介護職員が「わざと」そのような言動に及んでいるのか否か、という職員の自覚を問わず、客観的な状況を見てそれらの該当性が判断されるという点です。
高齢者虐待防止法は、広い意味での高齢者虐待を「高齢者が他者からの不適切な扱いにより権利利益を侵害される状態や生命、健康、生活が損なわれるような状態に置かれること」と捉えた上で、高齢者虐待防止法の対象を規定したものということができます。
したがって、客観的にみて「不適切な扱いにより権利利益を侵害される状態や生命、健康、生活が損なわれるような状態」にあると判断されるのであれば、いち早くその状態を是正するために行政が老人福祉法や介護保険法の規定に基づき権限を適切に行使することが求められるのです(高齢者虐待防止法第24条参照)。
この事例では、本来複数名で介護すべきところを、人出不足を理由に一人での不十分なケアが常態化しており、それが原因で移乗介護の際等に花子の体や頭を色んなところにぶつけていました。体中にあった痣や、慢性硬膜下血腫はこれらの不適切なケアが原因と考えられ、行政は、職員がこのように花子を乱暴に扱っていた事態を踏まえて「身体的虐待」と認定したのです。
また、端坐位が困難な花子を座らせ、その場を離れるということから発生した顔面負傷の介護事故は、介護職員として求められる職務上の義務を著しく怠ったものと評価されてもやむを得ません。だからこそ、行政は、「介護・世話の放棄・放任」と認定したのです。
「虐待」という言葉から、それが「故意」だけに限定されるのだ、と考えるのは大きな間違いであることは理解頂けましたでしょうか。
この事例で、行政からの調査に抵抗するなどもってのほかです。
行政は、医師の所見や、介護記録等の客観的な資料を分析した上で虐待の認定をしています。虐待認定をされた介護事業者としてはこれを真摯に受け止め、改善に努める必要があります。
3.介護事業者が「高齢者虐待防止」に向けて実践すべきこと
(1)研修の重要性
令和3年度介護報酬改定項目には、「高齢者虐待防止の推進」が盛り込まれました。3年の経過措置期間が設けられたものの、さっそく取り組まれている介護事業者も増えています。
この取組みでは、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることが義務付けられますが、中でも筆者は、「研修の実施」が非常に重要であると考えています。
筆者は、毎年、様々な介護事業施設にて高齢者虐待防止研修を実施しています。
その中で、上述したように、「虐待」を正しく理解していないケースに数多く触れてきました。
「自分たちの施設では虐待はありません」という言葉を筆者は真に受けていません。
テレビなどで大きく報道されるような故意の刑法犯罪に至る虐待事件だけが「虐待」ではありません。
弁護士などの専門家の研修を定期的に受講することで、高齢者虐待とは何かを正しく理解することが何よりも重要です。
何気なく利用者に対して放った暴言、それを聞いていた別の職員が、「それくらいの暴言は許されるのだ」と勘違いする、徐々に職場のモラル全体が低下する、「これくらいはいいだろう」という暗黙の不適切なルールが職場に蔓延する、それをおかしいと思う人が職場から少なくなっていく・・・。
このような悪循環に陥っている事業所はありませんか。
自分たちがその状態に陥っていると、中々その異常性に気付けないものです。
研修を受けることは自分たちの状態を客観的に見つめ直すきっかけにもなりますので、積極的に研修を受けるようにしましょう。
(2)弁護士にすぐに相談できる環境の構築
事業所で虐待が発生したとき、また、虐待を疑う場面に遭遇したとき、自分だけで悩まず、必ず問題点をオープンにすることを習慣にして下さい。具体的には、すぐに上司に報告する癖をつけて下さい。そして、報告を受けた上司は、決して隠蔽せず、対応を検討して下さい。虐待問題の対応は、様々な法律問題に発展する可能性があるため、弁護士にすぐに相談できる環境を構築することを事業者として検討することが望ましいと思います。
虐待問題は、介護職員個人の問題ではなく、組織全体の問題です。
組織対応をしていく上でも、弁護士に相談した上で、組織としてどう対応していくのかを検討していくことは、この時代、益々必要になっていくプロセスでしょう。
真に高齢者虐待防止を目指す上で、自分たちだけではなく法律の専門家である弁護士と連携すること、それにより、現場全体で考えることが習慣化し、結果として介護サービスの質は高まっていくと思います。
*今回のテーマについて、さらに詳しく知りたい方はこちらをご一読ください:「介護現場の高齢者虐待!発生原因や適切な対応方法・防止策まで詳しく解説」