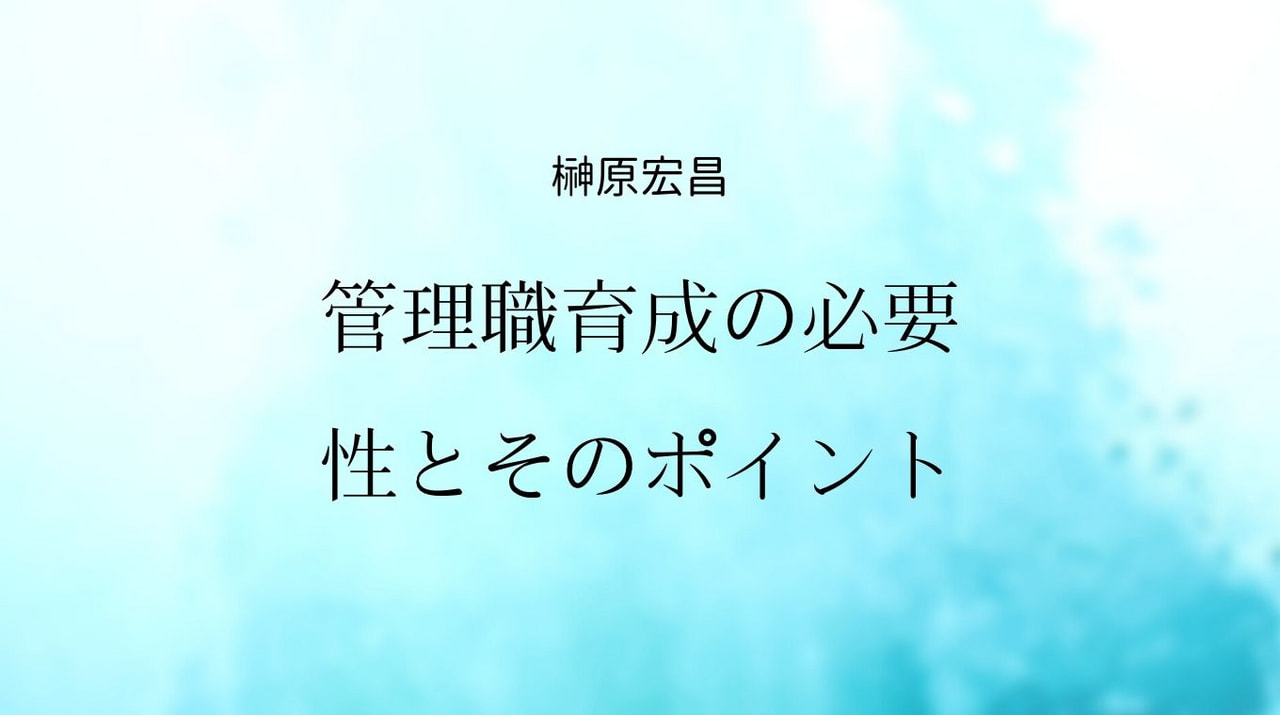現場職員と管理職とでは求められるものが異なる
介護現場では,介護職が管理職に昇進することが多いものです。現場の第一線で介護職として働いていた人が,いつの日にか,現場の管理者や主任という,いわゆる管理職を任せられます。管理職を任せられるということは,おそらく介護職として有能だから,そして人間的にも組織人としても他の模範となる人材だからだと思います。
ただし,これをお読みの皆様はすでに経験済みだと思いますが,一スタッフ,一介護職として求められる能力と,管理職として求められる能力は同じではありません。現場の第一線で必要とされる介護や看護の専門職としてのスキルに加えて,管理職としての,人の上に立つ,人をまとめるための勉強が必要になってきます。専門職としてのスキル研修に加えて,管理職のための研修が必要な理由はここにあります。
管理職として求められるものには以下のようなものがあるでしょう。
・現場のケア内容に責任を持つ(自らが実施したケアに対する責任だけではない)
・職員の育成に責任を持つ(自らが成長するだけでは評価されない)
・法令や収支に関する知識が現場職員以上に求められる
・組織の目標を達成するための計画を立てて、PDCAを回す(目の前のケアだけが仕事ではない)
こうしたことをふまえて、本稿では「管理職育成の必要性とそのポイント」について見ていきたいと思います。次回・次々回では「管理職が直面する3つの論点」「管理職は現場の何を見るとよいのか?」についてより具体的な内容をとりあげたいと思います。
管理職の辛さとやりがい・学び
前項で、一介護職と管理職の役割の違いについて触れましたが、私自身の実体験に基づいて、いくつか介護職から管理職になった時に感じた辛さや、その一方で感じたやりがいや学びについてご紹介します。
管理職は,担当する部署の管理・監督を任されている立場にあり,当然ではありますが,一スタッフとは異なる責任と権限を有することになります。私はよく,「管理職は担当部署全スタッフの一挙一動に責任がある」と言われいますが,つまり,部下のミスは上司の責任,部下のせいにはできないということです。これは好むと好まざるとにかかわらず,組織内においても社会的にもこのように見られるものです。
そんなつらい立場の中にあっても,ひとたび管理職となれば,あら探しをされてしまいます。一スタッフの時には「頑張ってるね」と褒められたことでも,管理職になると一生懸命に仕事をすることは当たり前のこととしか思われません。自分の身を犠牲にしてでも,部署や部下を守ることが要求されることも多々あります。やりきれなさを感じるかもしれません。放り出したくなることもあるかもしれません。大きな負担と重い責任。その重圧に押しつぶされそうになることばかりでしょう。
しかし,それは周囲から大きな期待が寄せられていることを意味しますし,現場に対する大きな影響力があることの証明でもあります。自分の思い描く職場を創造できるチャンスでもあるのです。またその過程で,かけがえのない仲間を得ることも多く,その喜びは何物にも代えられないものです。人間的にも,専門職としても大きな成長の機会となる。私はこれを,ハイリスク・ハイリターンと呼んでいます。たとえハイリスク・ローリターン,つまり負担ばかりが大きく見返りが少ないと思える時期があったとしても,学べるものと得られるものが大きいということは,ぜひ頭の片隅でもよいので覚えておいてください。
管理職によって、業績、ケアの質、職員の育成・定着が変わる!
管理職の定義
管理職と言っても、法人や事業所の規模やサービス種別によっても、その内容は変わってきます。利用者100名の特養の施設長も管理職でしょうし、利用者10人のユニットのリーダーも管理職です。50名定員の通所介護の管理者もいれば、10名定員の地域密着型通所介護の管理者もいます。職員3名の居宅介護支援事業所の管理者もいることでしょう。
ただ、規模の大小、サービスの内容にかかわらず、その事業所、組織、チームは、管理職によって相当程度影響を受けることを理解しておく必要があります。つまり、事業所の業績やケアの質、そして、職員の育成や定着に大きな影響がある、ということです。
業績について
業績は主に稼働率で決まります。介護保険事業の場合だと、多くの場合は居宅介護支援事業所のケアマネジャーか病院の相談員から利用者の紹介を受けて、サービス利用につながるでしょう。その際、サービスの内容、質はもちろん大切ですが、やはり、そのサービスの責任者である管理職のスキルや熱意、人柄といったものが見られているものです。
紹介する側にも責任があるわけで、ケアマネジャーにしても相談員の立場から考えれば、いいかげんな事業所は紹介できません。安心して任せられる事業所であるかどうかが問われている、ということです。そして、それは管理職の資質によるところが大きいものです。
ケアの質について
また、事業所のケアの質、サービスの質も管理職によるところが大きいでしょう。その事業所の責任者である管理職が、何をよしとして、何を評価するかによって、日々のサービスは大きく変化します。もちろん法人単位でケアやサービスの質を担保すべく、方針やマニュアル、研修をきちんと整備しているところなら、管理職1人の影響力はまだ薄くなりますが、そうした法人が少ないのも介護業界の現状ではないかと考えます。
職員の育成と定着について
介護職の中に、ケアやサービスの質について、よい意見や発想を持っている人がいたとしても、リーダーである管理職にその気がないと分かれば、意見を言わなくなるものです。そうなると、やりがいを見い出すことができない優秀な職員は、その職場を去っていくこともあり得ます。やはり、自分の力が認められ、発揮できる職場で働きたいものです。
さらに、複数の職員を束ねる管理職に、えこひいき、不公平等があって、それを介護職が不満に思っているという話も、介護現場ではしばしば耳にします。これも職員の退職を促す一つの理由になり得ます。
以上、管理職によって、業績、ケアの質、職員の育成・定着が変わる、ということがお分かり頂けたでしょうか。
管理職の「管理・育成」の重要性
ただ,「さあ,今日から管理職!」と言っても,「そもそも何をすべきなのか分からない」「何を管理するのか分からない」という悩みもよく聞きます。そして,その上司も管理職の業務についてきちんと教わったことがないので,体系的に教えることができないというのが実際ではないかと思います。管理職として,何を見て,何を管理し,何に責任を持つのか,明確でないことがほとんどでしょう。
このあたりの具体的内容は、また次回、次々回のテーマとして扱っていきますが、 いずれにしても、管理職の「管理・育成」が非常に重要だということは、ご理解頂けると思います。
私も研修講師やコンサルティングの仕事をしていて、管理職育成をテーマとすることが多いですが、法人内で管理職の育成について、責任を持って取り組んでいる人がいない、という現場によく遭遇します。管理職の育成が大切だ、と言っておきながら、誰もその課題に責任を持っておららず、具体的な取り組みがなされていない法人・事業所が多いものです。
そういう状況だからこそ、私が呼ばれるのでしょうが、外注で、しかも月1回程度の指導で、複数人の管理職の育成が十分にできると思う方が間違いでしょう。もちろん、外部の人間に任せた方がうまくいく内容もありますので、私の理想は、外部の専門家と内部の責任者がタッグを組んで、現状と課題を共有し、ともに課題の解決を目指す、という図式です。こういうことが具体的な形として取り組めている法人では、やはり成果が出るのも早いです。
ということで、いかがでしたでしょうか。今回は「管理職育成の必要性とそのポイント」というテーマで、「現場職員と管理職とでは求められるものが異なる」「管理職によって、業績、ケアの質、職員の育成・定着が変わる!」「管理職の管理・育成の重要性」について見てきました。管理職育成における基本的な考え方の理解につながればうれしいです。