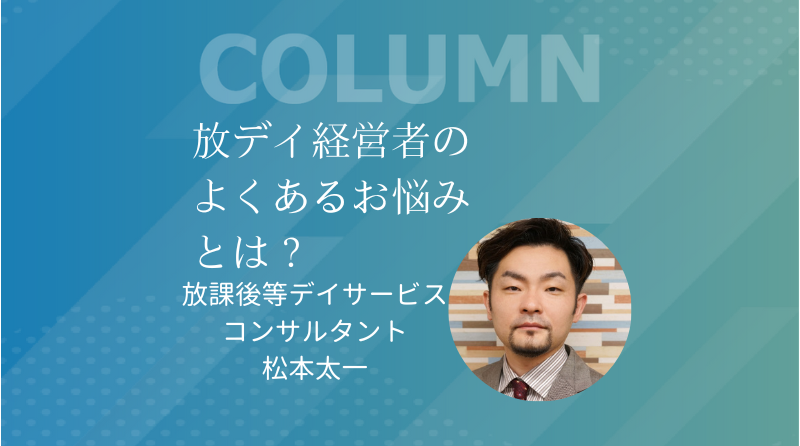放課後等デイサービスコンサルタントの松本太一です。
今回は、放課後等デイサービスを運営する経営者からよく聞かれる質問やお悩みにお答えします。これから参入を考えている方にも、ぜひ事前に心構えいただきたい内容ばかりですので、ぜひご覧ください。
*これまでの連載はこちら
Q1.「経営者も支援の現場に入るべきか?」
とてもよく聞かれる質問です。
法人の状況によりますが、基本的には「迷ったら現場に入ったほうがよい」とお答えしています。
正しい経営判断をするには、現場の状況を正しく把握しなければなりません。そのために一番有効な方法が、自分が支援者として現場に入ることです。
例えば、ある教材を導入したとしましょう。かかった費用は定量的に把握できますが、それがどのくらい子どもたちに良い影響を与えているかは、自分が現場に入って実際にその教材を使ってみないとわからないものです。
そして、そこがわかっていないと、支援上必須になる教材の購入費用を出し惜しみしてしまったり、逆に、営業マンの上手なトークに惑わされて高額な教材を導入したのに現場ではちっとも活用されていない、さらに悪いことにそれに気づけなかったり―といったことが起こります。
経営者が現場に入ることで、導入した教材や施策が、コストに見合った成果を挙げているのかを見極めることができます。この“見極め”の過程を繰り返すことで、経営的側面と現場の実情の両方に即した経営判断ができるようになります。
経営者が放デイの現場に入ることの弊害
他方で、経営者が現場に入ったときの弊害として、支援員が経営者に気を使ってしまい子どもと向かいあう余裕がなくなることや、経営者の思い付きによる行動や言動が原因でチームとして秩序だった動きができなくなってしまうことがあります。
しかし、これは経営者が現場に入ること自体が問題なのではありません。管理者や児発管を飛び越えて、経営者が直接支援員に指示を出してしまったり、現場のルールを無視して動いてしまったりすることが問題なのです。
こうした弊害を防ぐため、経営者が現場に入る際は、あくまで現場の責任者である管理者や児発管の指示のもと、一支援員としての役割に徹することが必要です。その中で気づいたことがあれば、子どもたちが帰った後で、管理者や児発管に伝えましょう。
もう一つ大切なポイントは、自分が支援に入る日と時間帯を明確にすることです。手が空いたときフラッと現れて、いつの間にかいなくなってしまうようでは現場にとって戦力にならず、かえって煩わしい存在になってしまいます。
そうではなく、「今週は火曜日と木曜日に入ります。ただ、木曜日は5時から外出があるので途中までの支援になります」と管理者に事前に伝えておくことが必要です。
このように節度を守って現場に入ることができれば、「現場の状況がわかっていて、力にもなってくれる経営者」としてスタッフの信頼を得ることができるはずです。
経営者が現場に入らないほうがよい場合
明確に現場に入るべきではないタイミングもあります。それは、経営者としての仕事が済んでいないときです。
例えば、支援員から「こういう教材を購入してほしい」と要望を受け、経営者が「今、色々立て込んでいるからしばらく考える」と答えておきながら、現場にでて支援を始めたら、支援員は「その前にやることがあるのでは・・・?」と疑問や不満を抱いてしまいます。
経営者として他にやるべきことがあるにも関わらず支援に入ってしまう。このような傾向は、支援者を経て経営者になったばかりの方に多く見られます。経営よりも支援のほうが慣れておりストレスが少ないので、どうしてもそちらに向かいたくなってしまうのですが、そこは経営者としての役割を優先させることが、支援員の信頼を得る上で大切です。
Q2.十分な数の支援員を揃えたはずなのに現場から「人が足りない」と言われる
これもよく聞かれる悩みです。実際に現場を見ると、人が充分足りている場合と、全く足りていない場合のどちらもあります。
いずれにしても、問題は、経営者と現場スタッフ双方の間で「いつ、どれだけ人手が必要なのか」きちんと認識をすり合わせできていないことにあります。そのため、経営者と支援人がお互い都合の良い解釈をしてしまい、意見の対立が起きているのです。
解決するには、お互いにしっかりコミュニケーションして、正しく現況を共有し、共通認識を持つ必要があります。具体的には下記のポイントを話し合ってみましょう。
対応策①足りないのは支援員かドライバーかを確認する
送迎を実施している事業所でよくあるのは、「直接支援する人員は足りているが、お子さんを送迎するドライバーが足りていない」ケースです。特に学校へのお迎えは、利用児の下校時間に合わせる必要があるので、事業所の都合で時間を動かしたり数を減らすことができません。迎えに行く学校が多かったり、お子さんの下校時間にばらつきがあり、同じ学校に複数回迎えにでなければならない場合は、送迎に必要なドライバーの数が多くなって、出勤している支援員だけでは対応できなくなります。それが「人が足りない」という現場からの訴えになるのです。こうした場合は、支援員を増やさずとも、専任のドライバーを雇うことで問題が解決します。
経営者として留意すべきなのは、現場からは「支援員は充分揃っているが、ドライバーは足りていない」という正確な報告は期待できないことです。なぜなら現場で働く支援員にとって支援する人数が多いに越したことはないので「支援員は充分揃っている」という報告は経営者にあげたくない心理が働くためです。
そこで、現場の管理者に「足りないのは支援員なのかドライバーなのか?」をしっかり聞き、現場にも入って現状把握することが課題解決に繋がります。
対応策②支援のスケジュールと支援員の役割分担を明確にする
客観的にみると人数は充分なのに、当の支援員はみな「人が足りていない」と感じている現場が少なくありません。こうした現場でよくある問題点は、その日の支援スケジュールと支援員の役割分担が明確になっていないことです。
こうした事業所では、どんな活動をするかを子どもたちがきてから支援員同士で相談していたり、1人の子どもにトラブルが起きるとその子に2人、3人の支援員が対応してしまうといった場面がよく見られます。そのため効率の悪い支援となっているのです。
こうした状況を防ぐには、その日の支援時間中、子どもたちにどのように過ごしてもらうのかを決めるタイムスケジュールを作り、ホワイトボードなどで書き出すのが有効です。
そのスケジュールにもとづいて、支援員の役割も明確にします。具体的には、全体の司会や他の支援員への指示出しを行う“リーダー”1名と、個々の子どもたちに臨機応変に対応する“サブ”の役割分担をはっきりさせることが大切です。
この2点については、過去の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
経営者からいただく質問はまだまだたくさんあります。次回も引き続き、お答えしていきます。