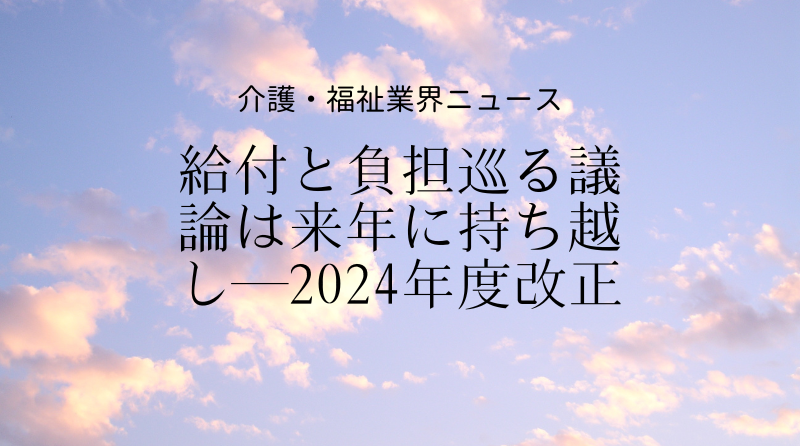社会保障審議会・介護保険部会は19日、2024年度の介護保険制度改正に向けた提言のとりまとめに向け、年内最後の議論を行いました。今回の議論を踏まえ、最終版が年内に公表される見通しです。
(*追記:20日に最終版が公表されています。本ページに記載の内容に変更はありません)
しかし、次期制度改正で「給付と負担」の見直しをどのようにを行うべきであるか、その結論は来年以降に先送りとなりました。
厚生労働省は最新の提言案に、それぞれの課題について結論を出す期限や目標などを設けています。例えば、2割負担の範囲の拡大については次期改正までに結論を出し、要介護1、2を対象とした訪問介護や通所介護を総合事業に移行するかどうかは、27年までに結論を出すべきとしています。
介護保険部会としての提言の全体像
同部会による提言(介護保険制度の見直しに関する意見(案))では、これまでの介護保険部会での議論の経緯や、24年度の介護保険制度改正で解決すべき課題、そのためにとるべき対応をまとめます。
最新の案は、前回の委員らの要望や政府の全世代型社会保障構築会議の報告書(12月16日)を受けて修正などが加えられ、以下の構成となっています。
はじめに
Ⅰ地域包括ケアシステムの深化・推進
1.生活を支える介護サービス等の基盤の整備
2.様々な生活上の困難を支え合う地域共生社会の実現
3.保険者機能の強化
1.介護人材の確保、介護現場の生産性向上の推進
(1)総合的な介護人材確保対策
(2)生産性の向上により、負担が軽減され働きやすい介護現場の実現
2.給付と負担
(1)高齢者の負担能力に応じた負担の見直し
(2)制度間の公平性や均衡等を踏まえた給付内容の見直し
(3)被保険者・受給者範囲
おわりに
2割負担の拡大・老健と介護医療院への多床室導入を引き続き検討
提言案では初めて明文化された「給付と負担」の見直しを巡る検討については、テーマを「高齢者の負担能力に応じた負担の見直し」と「制度間の公平性や均衡等を踏まえた給付内容の見直し」、「被保険者・受給者範囲」に大別して、再整理されています。
意見の隔たりが大きい論点については、給付範囲の縮小や負担拡大に対して推進・賛成派の意見と慎重・消極派の意見が併記され、その後にいつ、どのように今後議論を進めていくのか、そのためにどのような材料が必要であるかなどが記されています。
(1)高齢者の負担能力に応じた負担の見直し
まず、高齢者・利用者層負担の見直しについてです。
1号保険料負担の在り方
- 介護保険制度の持続可能性を確保するためには、低所得者の保険料上昇を抑制することが必要であり、負担能力に応じた負担の観点から、既に多くの保険者で9段階を超える多段階の保険料設定がなされていることも踏まえ、国の定める標準段階の多段階化、高所得者の標準乗率の引上げ、低所得者の標準乗率の引下げ等について検討を行うことが適当である。
- 具体的な段階数、乗率、低所得者軽減に充当されている公費と保険料の多段階化の役割分担等について、次期計画に向けた保険者の準備期間等を確保するため、早急に結論を得ることが適当である。
- 現役層(40~64 歳)が負担する2号保険料について、(中略)透明性を確保する観点から、毎年、納付金額決定の後の介護保険部会等で厚生労働省から報告することが適当である。
- 2号保険料については、国の審議会という開かれた場で検討・議論し、大臣は審議会の意見を聞いた上で、全国一律の保険料率を 決定するというような透明性、納得性のある仕組み、手続等に見直すことが必要との意見があった。
このテーマでは、65歳以上の人の保険料について、高所得者の負担を引き上げる一方で、低所得者は引き下げを行い、メリハリづけを行う方針が示されています。
2号保険料(40〜64歳が負担)については、保険料そのものの見直しをすぐに行うのではなく、見直しの内容や金額の改正について透明性を高める方向性が示されました。
「現役並み所得」、 「一定以上所得」の判断基準
- 「一定以上所得」(2割負担)の判断基準について、 後期高齢者医療制度との関係、介護サービスは長期間利用されること等を踏まえつつ、高齢者の方々が必要なサービスを受けられるよう、高齢者の生活実態や生活への影響等も把握しながら検討を行い、次期計画に向けて結論を得ることが適当である。
- 「現役並み所得」(3割負担)の判断基準については、医療保険制度との整合性や利用者への影響等を踏まえつつ、引き続き検討を行うことが適当である。
2割負担の対象(所得の基準)拡大について、「次期計画に向けて結論を得る」と時期を示しました。先に公表された全世代型社会保障構築会議の報告書の内容を受けたものです。
年明け以降も介護保険部会で議論されることになり、検討の際に考慮すべき事項として
- 後期高齢者医療制度(22年10月から対象範囲が拡大済み)との関係
- 介護サービスは長期間利用されること
- 高齢者の生活実態や生活への影響
を示しています。
これに対し、3割負担(「現役並み所得」)の判断基準については、「医療保険制度との整合性や利用者への影響等を踏まえつつ、引き続き検討を行うことが適当」と少し弱い表現になっています。
議論の経緯について、2割負担や3割負担の対象を拡大することへの賛成意見と反対意見が併記されているほか、「マイナンバー制度の活用を含め、所得だけでなく資産も捕捉し勘案していくという観点も重要」との意見も記載されています。
補足給付に関する給付の在り方
- 補足給付に係る給付の実態やマイナンバー制度を取り巻く状況なども踏まえつつ、引き続き検討を行うことが適当である。
介護保険施設に入所する低所得者(住民税非課税世帯)の食費・居住費の負担軽減策である補足給付の見直しについてです。
見直しの方向性や時期は明記されていませんが、2割負担や3割負担の対象拡大についての議論同様、マイナンバー制度を活用した資産把握について検討を促しています。
(2)制度間の公平性や均衡等を踏まえた給付内容の見直し
多床室の室料負担
- 介護老人保健施設及び介護医療院の多床室の室料負担の導入については、 在宅でサービスを受ける者との負担の公平性、各施設の機能や利用実態等、これまでの本部会における意見を踏まえつつ、介護給付費分科会において介護報酬の設定等も含めた検討を行い、次期計画に向けて、結論を得る必要がある。
介護老人保健施設及び介護医療院の多床室の室料負担の導入について、来年から社会保障審議会・介護給付費分科会で引き続き検討を重ねます。24年度からの改正で対応するかどうか、結論をだそうとしています。
ケアマネジメントに関する給付の在り方
- ケアマネジメントに関する給付の在り方については、利用者やケアマネジメントに与える影響、他のサービスとの均衡等も踏まえながら、包括的に検討を行い、第10期計画期間の開始までの間に結論を出すことが適当である。
ケアマネジメントへの自己負担の導入も、意見の隔たりが大きい論点です。24年度の改正での対応を見送り、27年度の改正までに結論を出すことを明記しました。
軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方
- 軽度者(要介護1・2の者)への生活援助サービス等に関する給付の在り方については、介護サービスの需要が増加する一方、介護人材の不足が見込まれる中で、現行の総合事業に関する評価・分析等を行いつつ、第10期計画期間の開始までの間に、介護保険の運営主体である市町村の意向や利用者への影響等も踏まえながら、包括的に検討を行い、結論を出すことが適当である。
要介護1・2の高齢者への訪問介護や通所介護を市町村の総合事業へ移行する案です。この論点は、移行そのものに反対する意見のほか、受け皿の整備が不十分であり、検討そのものが時期尚早という見方も出ていました。そこで、24年度改正での対応を見送り、27年度までに「現行の総合事業に関する評価・分析等を行いつつ」結論を出すものとしています。
(3)被保険者・受給者範囲
- 介護保険を取り巻く状況の変化も踏まえつつ、引き続き検討を行うことが適当である。
第2号被保険者の対象年齢引き下げや、第1号被保険者の対象年齢引き上げについてです。後者は、一部の意見として触れられています。
財源や、サービス受給者の範囲を広げる(または狭める)という制度の根幹を見なおす論点ですが、まだ長期的な検討課題になりそうです。
ケアマネジャーの法定研修の受講費用の負担軽減などについて追記
また、今回示された提言案では、前回会合での委員からの指摘などを受け、介護サービス等の基盤の整備などに関する記載も一部修正されています。
例えば、
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(看護)小規模多機能型居宅介護の更なる普及
- ケアマネジャーの法定研修の受講費用の負担軽減
を進めることなどが追記されました。なお、提言書は今回も委員から文言修正を求める意見などが多数あったため、最終調整が行われたのち公表されます。