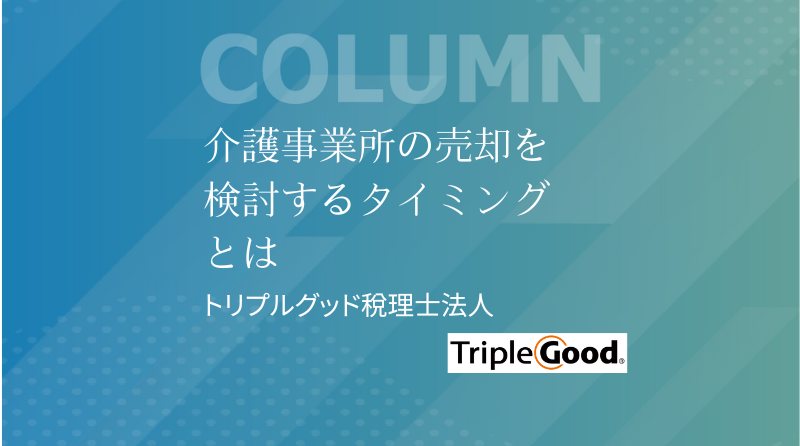東京商工リサーチの調査結果によると2022年1月〜9月の「老人福祉・介護事業」の倒産は、『100件』(前年同期51件)と急増し、過去最多となっています。
倒産が急増している要因として、介護職員の人材不足、新型コロナウイルス感染症のまん延による利用減少、そして光熱費や車輛燃料費などの価格上昇も大きく影響していると推測されます。
ここでは、経営状況が悪化してきたことを感じている経営者の皆様へ、『介護事業所の売却を検討するタイミング』と『事業を売却するまでの流れ』についてわかりやすく解説します。
介護事業所の売却を検討するタイミング
M&Aの最適なタイミングを見極めるのは難しいものです。将来的な不確定要素が多く、売り手の意思だけでなく買い手の存在があって初めて成立するため、タイミングの見極めには業界動向だけでなく、自社の業績も考慮することが重要です。
事業承継に少しでも不安のある方は、親族承継やMBO(社内承継)だけでなく、M&Aの可能性も常に視野に入れておきましょう。
企業を継続させるためには、自社の売却価格の査定などを事前にしておき、最適なタイミングで売却できるように準備しておくことも重要なことです。
まずは、企業の売却を検討するタイミングをみていきましょう。
赤字が継続しているとき
介護事業所の売却を検討するタイミングで、まず想定されるのが、赤字が継続している状況です。
今後の経営を見据えたときに、赤字が継続しており業績の回復が見込めない、もしくは難しい状況だと、経営破綻してしまう前に売却を検討する必要があります。
赤字が継続している、債務超過になっている、自社での業績回復が見込めないといった場合は売却できないと勘違いしている方が多いようですが、そういった状況でも売却の可能性は十分あります。こうした場合、早めに検討を進めるのがよいでしょう。
場合によっては、赤字になる前に売却を検討したほうがよいこともありますので、いずれにしても、まずは自社の売却の可能性の確認や売却価格の査定をしてみてはいかがでしょうか。
追加の運転資金を借り入れるとき
会社が赤字であることと会社の借入金があることは、同義ではありません。多くの企業は借金をした状態で経営をしていますが、利益が出ている企業もあります。
借入金の元金返済は経費にならないため、利益を原資として返済する必要がありますが、利益よりも借入金の返済額の方が多いと、お金は減り続けてしまいます。
そういった場合、利益は出ていても、追加の運転資金を借りる必要があります。
その結果、利益が出ているが、借入金が増え続ける状況となり、いずれ経営が破綻する可能性があります。
そういった状況では、追加の運転資金の融資を受ける必要のあるときが売却を検討するタイミングにもなります。
介護報酬改定や業界再編の動きがあるとき
介護報酬の3年ごとの見直しで、自社が提供するサービスによって報酬が増額することもあれば、減額することもあります。
また、法改正に伴う規制などへの対応や業界再編への大きな動きへの対応が困難になるケースもあります。
今後の報酬改定や業界動向を見据え、自社での対応が困難になることが予想される場合は、売却を検討するタイミングにもなります。
魅力的な売却価格を提示されたとき
M&Aの件数は年々増加傾向にあり、介護業界も例外ではありません。
なかにはM&Aを検討していなくても、同業他社から売却の打診を受けることもあり、提示される売却価格が思いもよらない高額で提示されることもあるようです。
提示された売却価格が魅力的であるかそうでないかは、自社の売却価格を査定して自身で理解しておかないと判断できないものです。
売却を検討している状況でなくとも、継続的、かつ、安定的な経営を見据えると自社の売却価格を知っておくことも重要なことです。
専門業者による無料査定のサービスもありますので、自社の状況を確認しておくのもよいでしょう。
財務諸表から経営状況を把握するためのポイントとは?
M&Aでの売却を検討するにあたり、自社の財務状況を理解しておくことも重要です。
財務分析とは、貸借対照表や損益計算書の財務諸表の数字にもとづいて、会社の状況を分析することです。企業の経営に改善点や問題点がないかチェックできれば、戦略的で安定した経営が可能となり、M&Aもスムーズに進みます。
分析指標にはいろいろありますが、まずは、「収益性」「成長性」「安全性」の3つのポイントをおさえ、自社の状況を確かめてみてはいかがでしょうか。
収益性(儲かっているか)
企業がどれだけ利益を出せているかを確認するための分析手法です。
利益が出ていなければ、企業の継続的な運営は不可能ですが、単に利益があればよいというだけでなく、経営上適切な利益が出ているかどうかを確認する必要があります。
・まずは利益がでているか
国税庁の発表によると、19年度の日本の企業の赤字割合は、赤字法人181万2,332社、普通法人276万7,336社で、65.4%となっているようです。
利益を出すだけでも大変な状況ですが、赤字の企業は、まずは利益を出すことが重要になります。
・適切な利益が出ているか
多くの企業は銀行から融資を受けており、毎月返済する必要があります。
借入金の元金返済は経費にならないため、利益を原資に返済する必要があります。
しかも利益が出た場合は、法人税を支払う必要がありますので、下記の状況でないと、利益が出ても、お金が増えないこととなります。
利益 ー 法人税(利益の35%)= 自由に使えるお金 > 年間の元金返済額
単に利益が出ているかどうかだけではなく、お金が増え続ける経営を目指すのが重要です。
成長性(のびているか)
安定的な経営を行うためには、企業の成長が不可欠です。
現状維持では、あらたな設備投資、優秀な人材の採用や離職防止などの対策が難しくなります。そのため、財務分析においても成長性の確認が重要です。
その際、売上だけでなく利益も伸びているか把握しましょう。
前期よりも少しでも売上、利益とも成長できるようにしたいものです。
・売上がのびているか
増収率(%)=(当期売上 ー 前期売上) 前期利益 ✕ 100
・利益がのびているか
増益率(%)=(当期利益 ー 前期利益) 前期利益 ✕ 100
安全性(つぶれにくさ)
利益が出て成長してても、お金がつきると企業経営は継続できません。
そのため、自社にどの程度の支払い能力があるか、また、資金不足になったときに銀行から追加融資を受けられるかが重要となります。
・自社の支払い能力の確認
介護事業の場合、売上の入金が2カ月後になることから、他の事業よりも手元の運転資金は少し多めが望ましいです。
具体的には、毎月の経費や借入金の返済額の合計の3〜6カ月程度あれば望ましい状態であるといえます。
現預金残高 > (毎月の経費 + 毎月の元金返済額)✕ 3~6カ月
・追加融資の可能性の確認
銀行が企業の財務分析をする指標で、借入金月商倍率というものがあります。
借入金 月商(月あたり売上) = ●●
たとえば、年商1億2,000万円、借入金が3,000万円の場合、平均月商は1,000万円ですから、
3,000万円1,000万円で、借入月商倍率は、「3」となります
売上と借入金のバランスを確認する指標ですが、倍率が6倍をこえると追加融資が難しくなると言われてますので、追加融資の枠を確かめながら経営するのがよいでしょう。
介護事業所の事業売却・事業譲渡の流れ
いざ売却しようにもその手続きは専門性が高く複雑です。ここでは、企業売却の手続きの流れについて解説します。
M&A仲介サービスに相談する
会社の売却にはさまざまな手続きが必要で複雑です。自社だけで行うことはほとんど不可能ですから、専門業者のサポートを受けることをお勧めします。
また、無料で自社の売却価格の査定をしてくれるサービスもありますので、自社の状況を理解するためにも専門業者へ相談しましょう。
M&A仲介サービスの契約を結ぶ
M&Aは秘密厳守で進める必要があるため、専門業者と機密保持契約、業務委託契約の締結をしたうえで進めます。
自社だけで行う場合や専門でない業者のサポートを受けると、売却情報の漏洩などトラブルにつながりかねないため、信頼できる専門業者のサポートを受けることをお勧めします。
買収企業とのマッチング
自社の企業価値算定後、買い手候補のリストアップを行ってもらい、売却可能性のある企業を絞り込み、守秘義務契約を結んだうえで売り手企業情報を開示し、買い手企業の選定を行います。
トップ面談
買い手企業の絞り込みの後、売り手企業と買い手企業とのトップ面談を実施し、双方の意向や経営に対する考え方などを確認して、次のステップに進めるかどうかを検討します。
基本合意
トップ面談後、双方に合意の意思があれば、基本合意の締結となります。
基本合意契約書は、最終合意に向けた直前の契約書となり、売却価格、スケジュール、デューデリジェンス(リスク調査)など、M&Aの大まかな条件を決めることとなります。
最終合意
デューデリジェンス(リスク調査)の終了後、最終的な売却条件など詳細をつめて、最終合意契約の締結を行い、M&Aが成立することとなります。
まとめ
M&Aは、売り手だけでも、買い手だけでも成立することはありません。
双方のニーズがマッチしてはじめて成立するものです。
経営をしているとよいときもそうでないときもあります。
継続的な安定した経営を行うためにも、親族承継、MBO(社内承継)、M&Aと常に選択肢を広げ、事前準備しておくことが重要です。
M&Aについて可能性があると思う方は、最適なタイミングで売却できるように、自社の売却価格を査定してもらうなど、事前準備しておくことをお勧めします。
カイポケが提供しているカイポケM&AサービスではM&Aに関するあらゆるご質問を受け付けております。 気になる点があればぜひ一度、相談してみてはいかがでしょうか。
*カイポケM&Aサービスはこちら
*注:<赤字割合データ元>