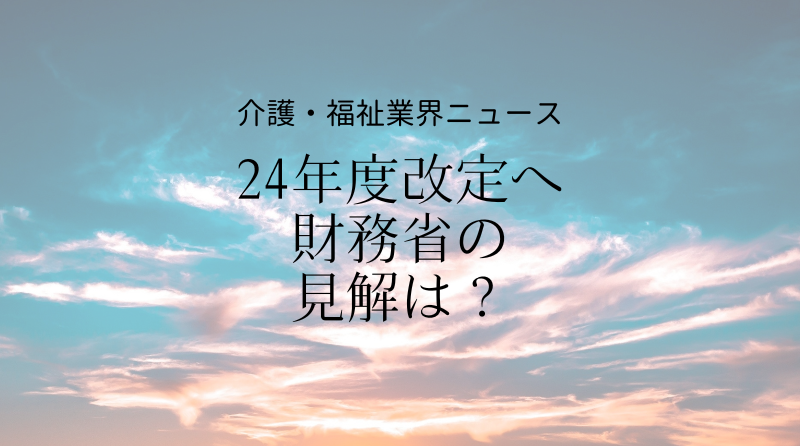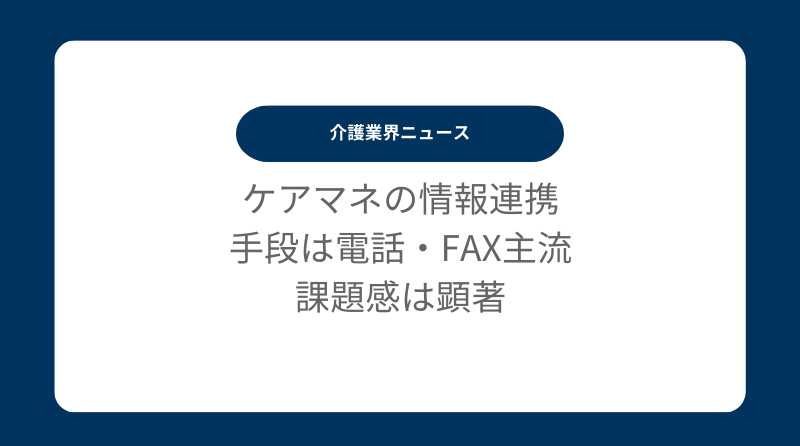財務省が9月末に開いた財政制度等審議会(財務相の諮問会議)の分科会では、社会保障施策の財源を巡って議論が行われました。
同省は、こども・子育て施策の強化にあてる財源を確保するためにも、医療や介護などの施策に係る費用を抑えるべきとして、2024年度報酬改定での対応を訴えています。
介護分野については、人員配置基準の柔軟化などの施策を強力に進めることで事業者の収入増につなげ、「現場の従事者の賃上げにつなげる好循環を実現することが必要」と指摘しています。
2024年度報酬改定の動向を読むうえで、財務省の基本認識についても確認しておきましょう。
2024年度の政府予算の編成に向けて社会保障費が議題に
24年度の政府予算の編成に向けた提言の取りまとめに向けて、財務省は9月27日に財政制度等審議会(財務相の諮問機関)の財政制度分科会を開きました。
提言は例年、11月下旬〜12月の初旬にまとめられるもので、この日は日本の経済や財政の現状のほか、医療・介護など社会保障が議題になっています。
医療・介護等の費用抑制し子育て政策の財源を拡充
財務省の資料では社会保障関連の施策や制度の見直しに当たって、医療や介護について論じる前に政府が6月に決定したこども未来戦略方針の内容についてまとめています。
概要は以下の通りです。
政府のこども未来戦略方針に盛り込まれている施策等(財務省の資料より)
- 児童手当や育児休業給付の拡充
- 「こども誰でも通園制度」(仮称)の創設
- 幼児教育や保育の現場における保育士の配置基準を改定
- 2026年度までに年3兆円台半ばの追加予算を確保する

(【画像】政府の「こども未来戦略方針」についての説明資料│財政制度分科会(9月27日開催)資料より)
ここで「3兆円半ば」としている追加予算の財源として政府は、医療や介護など既存の社会保障費の削減と、「支援金制度」(社会保険料による徴収を想定。詳細は年末までに結論)の創設をするとしています。
(*詳細は「こども未来戦略方針」)

(【画像】こども・子育て政策の財源についての説明資料│財政制度分科会(9月27日開催)資料より)
資料ではこのほかに、医療・介護の保険料率上昇を抑制する取組みを強化する必要性などについて触れられています。

介護分野の新たな改革案は見られず
では、財務省は医療・介護保険制度について見直しを提案しているのでしょうか。
今回の資料では、”物価上昇率を上回る報酬単価増への対応(診療所における1受診当たりの費用など)や”コロナ補助金などによる内部留保の活用”など特に医療分野の改革に比重が置かれています。
対して、介護分野については
- 多床室の室料負担など、制度間の公平性等を踏まえた見直し
- 介護保険の1号保険料の在り方の見直し
- 利用者負担における”一定以上所得”の判断基準の見直し
- 金融所得・金融資産を勘案した負担
を求めるなど、従来から指摘されてきた内容に留まっています。


その上で、24年度報酬改定における「主な課題」としては、構造的な人手不足の下でいかに需要に対応するかを挙げています。
これに関連して、介護職員等ベースアップ等支援加算の実績として
- 介護職員の賃上げが予算額を大きく上回ったこと
- 同加算の直接の対象ではない職員の賃上げも実施されていたこと
に触れ、今後の方策としては、職場環境の改善や生産性の向上(テクノロジーの導入や人員配置基準の柔軟化)を通じて、業者収入を増やし、「賃上げにつなげる好循環を実現することが必要」としました。
また、その前提として、費用負担や配分の見える化を強化していくべきとして、職種別給与・人数の見える化などを例示しています。
診療報酬の改定率プラスに厳しい視線も
分科会委員の意見のうち、介護や医療の制度改革や報酬に関するものでは以下のようなものがありました。
財務省の説明にもあった医療費の1受診当たり単価の上昇などを踏まえ、診療報酬の改定率には厳しい見方も出ています。
- 子育てを担う現役世代の負担を抑制するため、医療介護についても、年金のマクロスライド的な仕組みの導入や、全体の社会保険料率に上限を定めることも検討すべき。
- 歳出改革について、医療・介護の過剰な支出を削減すべき。収入面においても、高齢者の窓口負担の検証、資産と所得を把握して、応能負担を求めるべき。
- 年々増える社会保険料負担が現役世代の手取りを縮小させている。こども未来戦略方針にも記載されている通り、現役世代に配慮し、実質的な負担増とならないように社会保障の給付の抑制に努めていく必要がある。
- 医療・介護について、報酬がきちんと分配されているか、厳しい方もいるが、一部の方が高給を取っているのではないかという点も含めてよく検証する必要がある。病院・診療所などもよく分けて分析し、単に物価増に基づいて報酬を引き上げることは避けるべき。
- 医療・介護の報酬改定率について、データに基づいて必要な水準をよく考える必要がある。雇用者報酬より給付が伸びるのはサステナブルではない。
- 医療費の1受診当たりの単価が上昇する中で、コストの一部である医療従事者の賃上げは十分可能。今後公表される利益率を見て、必要であれば適正な水準に単価を下げることも視野に入れるべき。
- 単価増が起きている中で、更に改定率をプラスとすることは、保険料引き上げ・手取り減となり、政府が進める物価高対策とも矛盾する。
- 介護の処遇改善加算により、加算対象以外の方の賃上げできたことは好ましい。更なる見える化・経営の協働化・合理化が必要。リテラシーも含めてICT導入を進めるべき。