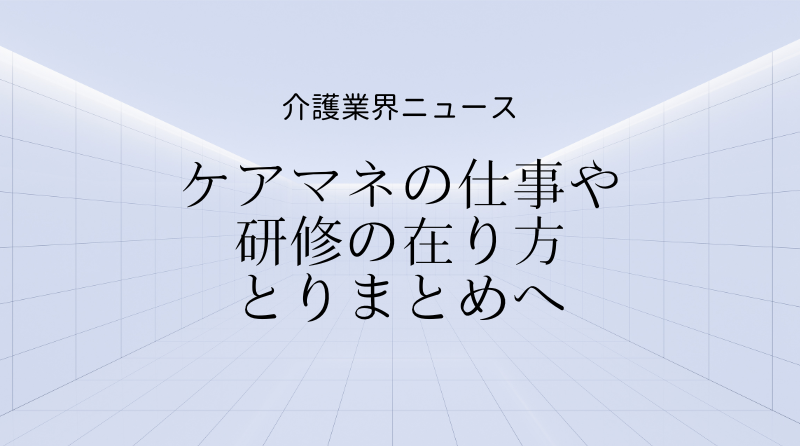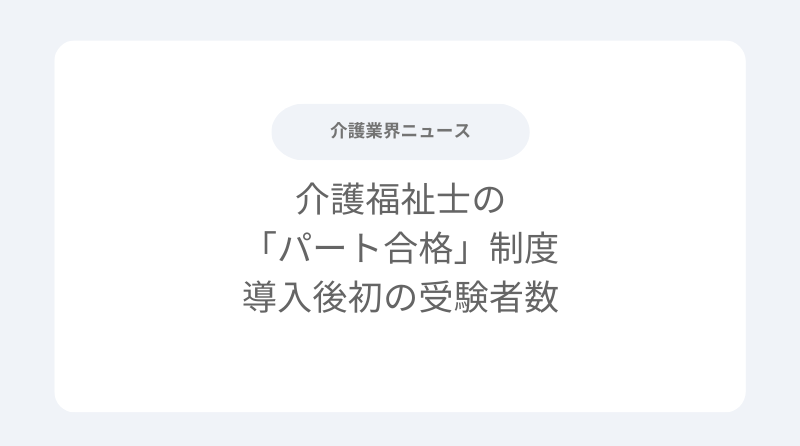介護支援専門員(ケアマネジャー)の業務範囲を整理し直してコンセンサスを得ようとする試みや、受験資格の見直しといった制度の根本にまで議題が及ぶことで注目を集めている厚生労働省の「ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会」。
同省は11月7日に「中間整理」の素案を示しました。
居宅介護支援事業所で働くケアマネが対応しているものの、報酬のつかない業務を「他機関につなぐべき」などと明示している点は、注目に値するでしょう。
最終的なとりまとめは居宅介護支援事業所の運営やケアマネジャーの業務に影響を与える可能性が大きいものですので、ポイントをおさえておきましょう。
検討会のテーマ”ケアマネジャーを巡る課題”とは
2024年4月に設置された「ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会」では、ケアマネジャーや主任介護支援専門員(主任ケアマネジャー)の役割、位置付けを改めて整理することなどを目的としてこれまでに4回話し合いが重ねられててきました。(※検討会構成員名簿)
近年における医療ニーズの高まりや世帯が抱える問題の複雑化など、ケアマネジャーが対応せざるを得ない相談が多種多様になってきていることが背景にあります。また、将来的にケアマネジャーの担い手不足が懸念されることへの問題意識から、人材確保・定着策も議題とされてきました。
具体策としては、実務研修受講試験の受験資格の見直しなど、制度や資格の根本に関わる論点も俎上に載せられています。
ケアマネジャーの業務・法定研修の在り方など4つの論点を整理
今回、厚労省が示した検討会の「中間整理」素案(正式な「中間整理」をまとめるためたたき台)は以下の4つのテーマと論点、それに沿った検討会の意見で構成されています。
最終的な取りまとめは、今後の制度改正にも一定の影響を及ぼすでしょう。




注目テーマ①居宅介護支援事業所におけるケアマネジャーの”業務の在り方”
「中間整理」素案のポイントとしてはまず、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが実施している業務が、法定業務の範囲であるか、そうでないかといった視点から分類されたことが挙げられるでしょう。

(【画像】第5回ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会資料より)
厚労省は上の表のように、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが実施している業務を
- 法定業務
- 保険外サービスとして対応しうる業務
- 他機関につなぐべき業務
- 対応困難な業務等
このうち、1の法定業務については、
- アセスメントやモニタリング等、利用者と直接関わるもの
- 給付管理をはじめとする事務的な業務
があり、事業所内で「それぞれの業務の分担を検討することが必要」などとしています。
この書きぶりについては、「少なくとも専従の事務職員を常勤1名を雇用するほどの介護報酬は、居宅介護事業所にはついていない」(江澤和彦構成員・公益社団法人日本医師会常任理事 )との指摘があった以外に構成員からの反対はありませんでした。
一方、問題視されている②や③の業務としては、日常的な生活支援や福祉サービスの利用・利用料支払いの手続き、財産管理、死後事務といった業務が挙げられています。
こうした業務については、ケアマネジャーが保険外サービスとして対応するか、地域にあるほかの地域資源につないでいくべきとする意見がまとまりつつあります。
ただし、担い手の確保や育成の手立てについてはこれからの話し合いになりそうです。
注目テーマ②ケアマネジャーの「定着」策:待遇への言及も
素案の時点の記載ではありますが、人材確保・定着策については、「特にケアマネジャーとして従事している者が、引き続きやりがいを持って、業務に従事し続けられるようにすることが重要」 という記載があります。検討会の提言としては新たな人材を増やしていくことよりも、まずはケアマネジャーの定着策を進めていく必要があるという内容でまとまりそうです。
その手法としては、作成する書類の様式見直しやカスタマーハラスメント対策、シニア層の延長雇用等の環境整備に並び、
- 他産業に見劣りしない処遇の確保
の必要性が明記されています。
注目テーマ③受験資格の緩和:認める方向で一致も範囲については意見に相違
一方で、新規入職者を拡大する方策としては、介護支援専門員としての資格を得るための受験資格を拡大をするべきという意見がまとまりつつあります。
緩和の方向性としては、
- 受験対象とする国家資格の範囲の見直し等
- 実務経験年数要件の緩和(現行は5年)
の2つが挙げられています。実務経験年数を短縮するという方向性について目立った反対意見はありませんでしたが、受験資格の緩和については意見に違いがあります。

(【画像】ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会中間整理 素案(たたき台) より)
例えば、専門職団体の代表として参加している柴口里則構成員(一般社団法人日本介護支援専門員協会会長)は「幅広い職種資格等から受験を促し、法定研修によってケアマネージャーに必要な相談援助スキルを身につけていくことが重要」という立場を取り、「若者がダイレクトでケアマネージャーになれるようなスキーム作り」を求めています。
一方で、受験を認める資格の範囲には一定の制限を課すべきとする考え方や「学卒者であればいいという考え方は慎重を期すべき」(花俣ふみ代構成員・認知症の人と家族の会常任理事)という意見もありました。
注目テーマ④更新研修の在り方:検討会の場を越えてSNS等でも話題に
検討会の枠を越え、XのようなSNSなどにおいても当事者の負担の大きさが叫ばれているのが、介護支援専門員更新研修についてです。
10月の第50回衆院選で議席を伸ばした国民民主党が公約に掲げていることも話題になっています。

(【画像】国民民主党ウェブサイト「政策各論」より。赤枠は編集部で追加。)
今回の”素案”では「更新研修を含めた法定研修については、継続して実施することを前提としつつ、可能な限り経済的・時間的負担の軽減を図るべく、その方策について検討することが適当か」と記載されていますが、この点について染川朗構成員(日本介護クラフトユニオン会長)は、「更新という仕組みのもと、短期間に集中的に時間的・経済的な負荷がかかることや、必要な研修をタイムリーに受けることへの弊害もあることから、更新という仕組みを廃止して、研修のあり方を見直すべきと申し上げてきた」と反論しました。
最終的な「とりまとめ」は今後の検討の前提となるだけに、次回の会合でどのような修正がされるか、引き続き注目を集めそうです。