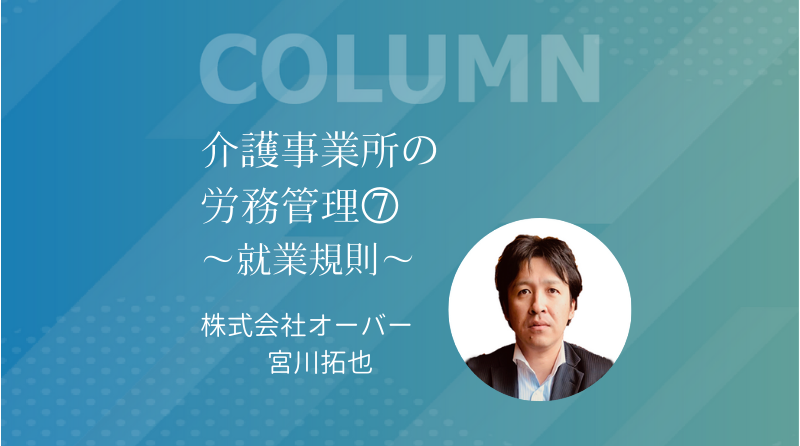第7回目は「就業規則のポイント〜なぜ就業規則が必要なのか(1)」についてです。
就業規則が必要な3つの理由
なぜ、就業規則が必要なのでしょうか?
1つ目の理由は、法律で定められているからです。
労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により、常時10人以上の従業員を使用する使用者は、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。これは法律ですので、遵守しなければなりません。
2つ目の理由は、会社(職場)のルールを従業員に伝えるためです。
これが重要です。
就業規則には必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、各事業場内でルールを定める場合には記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)とがあります。その他、使用者において任意に記載する事項もあります。以下を参考ください。
【絶対的必要記載事項】
①労働時間関係
始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
②賃金関係
賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
③退職関係
退職に関する事項(解雇の事由を含みます。)
【相対的必要記載事項】
①退職手当関係
適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
②臨時の賃金・最低賃金額関係
臨時の賃金等(退職手当を除きます。)及び最低賃金額に関する事項
③費用負担関係
労働者に食費、作業用品その他の負担をさせることに関する事項
④安全衛生関係
安全及び衛生に関する事項
⑤職業訓練関係
職業訓練に関する事項
⑥災害補償・業務外の傷病扶助関係
災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
⑦表彰・制裁関係
表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項
⑧その他
事業場の労働者すべてに適用されるルールに関する事項
これらが記載に関する事項です。
と同時に、「従業員に伝えるべき、伝わるべき」内容でもあります。
就業規則が必要な3つ目の理由として、就業規則は、会社を成長・発展させるためにあるものだからです。
この役割を果たすために、会社は仕事や職場についてどのように考え、従業員に何を求めているのかを記載し、それを伝える・伝わることが、就業規則が果たすべき役割であると考えています。
だからこそ、難しい言葉ではなく、分かりやすい言葉で記載する事、そして、人事労務運営が原因で経営が行き詰まらないように、想定される事態を盛り込んでおくことが重要となります。
では、就業規則の書き方について見ていきたいと思います。
就業規則の冒頭部分で経営者の考えを伝える
就業規則の冒頭は以下のような文言をよく見かけます。
(目的)
第○条 この就業規則(以下「規則」という。)は、労働基準法(以下「労基法」という。)第89条に基づき、 株式会社の労働者の就業に関する事項を定めるものである。
2 この規則に定めた事項のほか、就業に関する事項については、労基法その他の法令の定めによる。 (引用:厚生労働省 就業規則ひな形)
筆者は、この部分に、従業員の成長やキャリアの在り方、会社の成長・発展等に向けた想いを記載される事を提案します。
それは、会社の想いを理解した上で、就業規則を読むのと読まないのとでは、記載内容に対する従業員の理解度が変わるからです。
例えば、「会社は従業員の頑張りに誠実に向き合い、成長を応援する」「会社は働き方改革が進む社会において〇〇を大切に考えており従業員と共に成長していきたい」といった文言を入れておきます。
経営者の想いは、経営者が考える以上に従業員には伝わっていないと言えます。
こういったところで丁寧に浸透を図っていく取り組みが必要になってくるでしょう。
雇用区分の範囲と適用される規則の明確化がトラブルを防ぐ
(適用範囲)
第○条 この規則は、 株式会社の労働者に適用する。
2 パートタイム労働者の就業に関する事項については、別に定めるところによる。
3 前項については、別に定める規則に定めのない事項は、この規則を適用する。
(引用:厚生労働省 就業規則ひな形)
筆者が支援する企業でも、雇用形態が多様化しています。
「正社員」「契約社員(有期契約)(無期契約)」「短時間正社員」「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託社員」等。
だからこそ、まずは、その会社において正社員とはどのような雇用形態の者を示すのか定義をした上で、この就業規則は、どの雇用形態で就業する者に適用されるのかを明確に示しておく事がトラブル予防の観点から重要です。
例えば、「正社員:期間の定めのない正社員として雇用された者。契約社員(有期契約)(無期契約):期間を定めて又は期間の定めない雇用契約を締結した者で、契約社員として雇用された者」などと定義した上で、「本規程は正社員について定めたものであり、契約社員は契約社員就業規則、パートタイマーは、パートタイマー就業規則に・・・」とそれぞれについて定めます。
職場においては、“曖昧さ”がトラブルの原因となります。
例えば、正社員が自己の都合で病気等になり就労できない場合の「休職制度」について、契約社員はどのようなルールなのか、パートタイマーはどうかといった判断基準が必要です。
その前提として、雇用契約ごとに明確なルールを定めておく事が重要となります。
提出書類の規定と従業員の対応を入社後の評価に活用する
少し違った角度から、採用後に会社へ提出すべき書類についての規定について考えてみましょう。
以下のような規定を就業規則に盛り込みます。
(なお提出期日ですが、10日〜14日(2週間)を指定している事業者が多いと感じます。)
(採用時の提出書類)
第○条 労働者として採用された者は、採用された日から_週間以内に次の書類を提出しなければならない。
①住民票記載事項証明書
②自動車運転免許証の写し(ただし、自動車運転免許証を有する場合に限る。)
③資格証明書の写し(ただし、何らかの資格証明書を有する場合に限る。)
④その他会社が指定するもの
2 前項の定めにより提出した書類の記載事項に変更を生じたときは、速やかに書面で会社に変更事項を届け出なければならない。
(引用:厚生労働省 就業規則ひな形)
こうした規定を「約束された書類を約束された期日までに提出されるかどうかを入社後の評価」としている事業者があります。
もちろん、何かしらの理由で期日内に提出できない方もおられます。そのような事情であっても提出できない理由を事前にきっちり伝えているかが重要です。
業種、職種により求められる能力や成果は異なりますが、「社会人としての適性」を図る上では、ルールの遵守は効果的な指標です。
なお、書類が提出されず、そのまま放置することは避けなければなりません。
提出を促し、それでも提出されない場合は内容によって解雇事案となり得ます。
特に、業務に欠かせない資格を有する事を前提とする場合は就労してもらう事ができません。
このような事を防ぐために、選考時からその資格証の提出を義務づけるようにしましょう。
試用期間を制するものは、トラブルを制する?
試用期間を制するものは、トラブルを制する?
過言ではありません。筆者は、試用期間はとても大切な期間であり、会社全体として重要視すべき期間と考えています。
第○条 労働者として新たに採用した者については、採用した日から _か月間を試用期間とする。
2 前項について、会社が特に認めたときは、試用期間を短縮し、又は設けないことがある。
3 試用期間中に労働者として不適格と認めた者は、解雇することがある。ただし、入社後14日を経過した者については、第○条第○項に定める手続によって行う。
4 試用期間は、勤続年数に通算する。
(引用:厚生労働省 就業規則ひな形)
この規定でも問題ありませんが、試用期間で重要なことは、「会社が適切にその者の適性を把握できているか」「労働者が期間内に会社での役割について、入社時の認識とズレがないかを把握し、その是正ができているか」です。
労使それぞれに、「選考時・入社時は〜のように感じていたが、勤務すると〜の違和感がある」ということは珍しくありません。
だからこそ、試用期間にこの違和感を解消できるかが重要となります。
会社側からは「業務態度、能力、成果について想像以上の乖離がある」など労働者側からは「満足な指導がなされていない、疎外されている感じがする、このままでは不安」などといった、状況に蓋をしたまま本採用となると、後々にトラブルにつながる事があります。
そうした事態の防止策として、「試用期間の延長」と「本採用拒否」について記載することを提案します。
試用期間の延長についての記載とは、「試用期間中に本採用の可否を判断しかねると会社が認めた場合は、○カ月以内でこの期間を延長することがある」のような規定文です。
また、本採用拒否については、どのような場合に本採用拒否とするのかを記載します。
例えば「正当な理由のない遅刻、早退、欠勤等の不就労が複数回みられた場合」「学歴、経歴、資格などを偽っていたことが判明した」「採用選考の書類や面接時に本人が述べた内容が著しく異なっている」など。
ただし、試用期間の延長や本採用拒否には、試用期間だからといっても簡単には認められません。
「客観的に合理的な理由」と「社会通念上相当な要件」が求められます。規定に盛り込み、運用される場合は専門家のアドバイスをおすすめします。
ただし、試用期間の延長や本採用拒否には、試用期間だからといっても簡単には認められません。
「客観的に合理的な理由」と「社会通念上相当な要件」が求められます。規定に盛り込み、運用される場合は専門家のアドバイスをおすすめします。
特に、試用期間中、従業員との十分なコミュニケーションをとらなかったり、教育や指導をしていなかったりしておいて試用期間の延長や本採用拒否することはトラブルとなります。
試用期間の延長や本採用拒否の運用をする場合、試用期間中に従業員と定期的に面談して気づいた事の伝達、成果の確認、課題の確認、教育の実施をするほか、その従業員の関係従業員(上司等)と面談し同様の認識の共有が重要となります。
ご縁で入社した従業員さんが気持ちよく、意義を持って、会社に貢献いただけるためにも、試用期間は有効的に活用ください。
第8回目は、「就業規則のポイント②なぜ就業規則が必要なのか②」をお届けします。
※この記事は、難しい用語を極力削減し、わかりやすさを重視しています。
この記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。