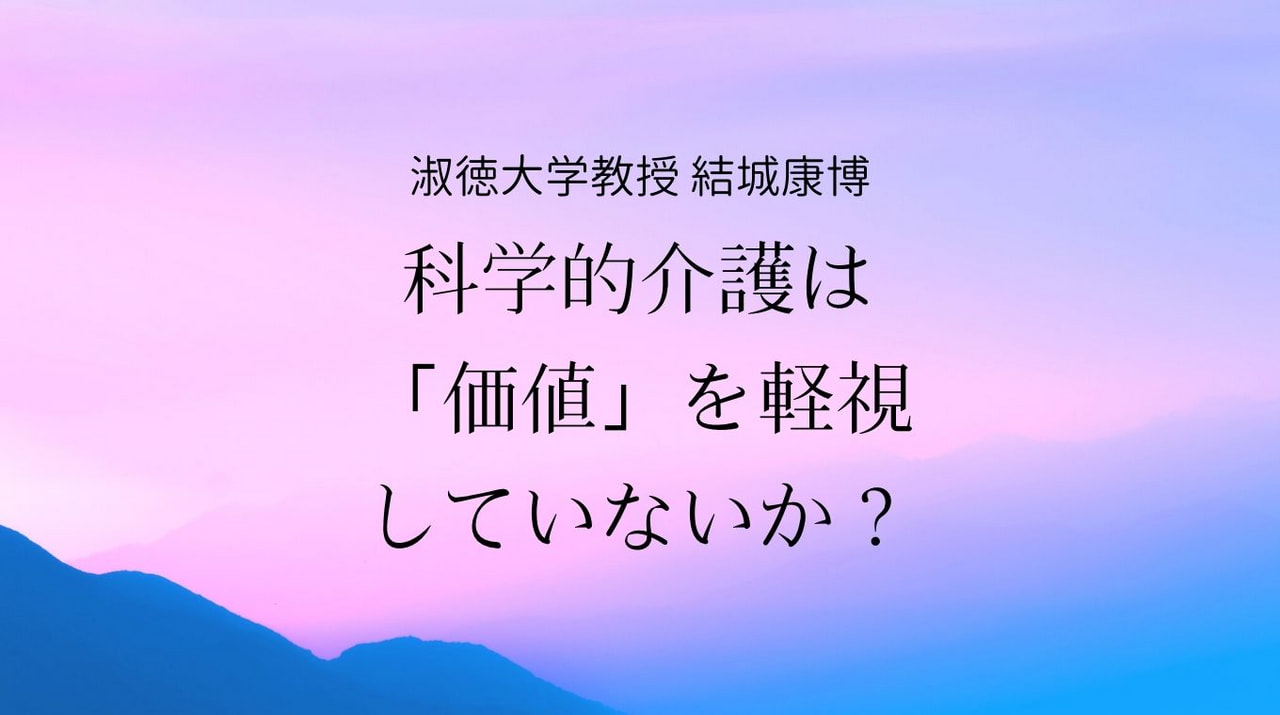21年介護報酬改定の目玉の1つ「科学的介護」は、始動当初から大きな課題に直面しているのではないだろうか?実際、新規利用申請に係るはがきの発送が遅延するなど、一部、スムーズな事務運営が難しく、提出すべきデータの猶予期間を令和3年8月10日と先延ばしとなった。また、現場の介護スタッフ等の意識はどうであろうか?科学的介護の意味を理解しながら前向きに取り組んでいるだろうか?本稿では、科学的介護の課題について考えてみよう。
1.介護経営者は「加算」を避けては通れない
介護経営者にとって科学的介護情報システム、いわゆる通称「LIFE(Long-term careInformation system)」を活用して、厚労省へ利用者の状態などのデータを提出することは、「加算」取得から考えれば避けては通れない。
特に、施設系介護事業所を中心に「科学的介護」は至上命題であり、より経営と介護報酬(主な対象ノ加算は下記に記す)について考えていかなければならない。
※対象の加算
科学的介護推進体制加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)、個別機能訓練加算(Ⅱ)、
ADL維持等加算(令和4年4月以降の加算算定に係るデータ提出)、
リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ及び(B)ロ、
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算並びに理学療法、
作業療法及び言語聴覚療法に係る加算、
褥瘡対策指導管理(Ⅱ)、
褥瘡マネジメント加算、
自立支援促進加算、
排せつ支援加算、
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)及び(Ⅲ)、
薬剤管理指導の注2の加算、
栄養マネジメント強化加算、
口腔衛生管理加算(Ⅱ)、
科学的介護推進体制加算、
栄養アセスメント加算、
口腔機能向上加算(Ⅱ)
2.介護現場の受け止め方
しかし、介護現場の受け止め方はどうであろうか?データ入力を誰が行うか?「PDCA」サイクルにおけるフィードバックによる介護サービスの提供をどうしていくか?これまでの業務から考えて、より「負担」が強いられると考える職員も多いと考えられる者も少なくない。
介護経営者は「事業収支」を踏まえれば、これらの「加算」取得は当然と考えるだろうが、現場の介護スタッフらは「やらされ感」に陥ると、モチベーションが低下する。しかも、実際の入力項目において、真の介護サービスのあり方に繋がる効果的なデータなのかと疑問に感じる介護スタッフも多いのではないだろうか?
本当に役立つデータがフィードバックされ、自分達の介護サービスに参考になるのであれば、モチベーションも上がるであろうが、厚労省が求めているデータは、医学系情報に偏り疑問と考えるスタッフも少なくないであろう 。
3.科学的介護と意思決定の背景
そもそも、「科学的介護」の考え方は、医療分野においては意思決定をするにあたっては「根拠」「価値」「資源(サービス供給量)」といった3要素が重要という「エビデンスに基づく医療(EBM)」が参考にされている(図1参照)。
この考え方を「科学的介護」に照らしてみると、医療と介護を比べると「価値」と「根拠」の部分で違いがあるのではないだろうか?
医療は「疾病」を対象としているため、そのサービスの効果を数値化しやすい。しかし、介護は「生活」をも対象としているため、提供されるサービス形態は援助者や要介護者・家族の「価値」観に大きな影響を及ぶす(図2参照)。確かに、科学的介護によって一定の介護サービスの普遍化は可能ではあるが、「価値」による部分が大きいので、医療のようにサービスの統一化は難しいと考える。
もちろん、誰しも科学的介護の促進には異論を唱える者はいないであろうが、介護においては医療のようにデータ重視とは必ずしもいかないことは認識しておく必要がある。

4.自立支援・重度化防止について
実際、「科学的介護」において、自立支援・重度化防止といった21年介護報酬改定の骨子とは大きな関連性がある。エビデンスを基に自立支援・重度化防止といった介護サービスが提供できることが目指されている。
しかし、90歳を過ぎた要介護者の全てが、今の状態よりも心身・介護度が改善して元気な時のような状態を望んでいるのだろうか?もちろん、そのように望んで「リハビリ」に励み、前向きに取り組む90歳以上の要介護者も多くいるだろう。重度の要介護者がおむつを外し、ベットサイドのポータブルトイレを活用して自分で排泄・排尿できるように望む者もいるかもしれない。
いっぽう、必ずしも自立支援・重度化防止にこだわらず、今の心身の状態が低下していても、穏やかに介護生活を送り、無理に努力して改善することを望まない要介護者もいるはずだ。
5.「介護」は生活の一部でもある
無論、筆者は「科学的介護」を否定するつもりはないし前向きに考えていくべきと考える。しかし、今の厚労省が推し進めている「科学的介護」は、医療モデルに偏り、本来の「介護」の意味を軽視しているのではないだろうか?
データで介護方針を考えていくことは重要であり、これまでの「介護」には欠けていた要素でもある。しかし、データに偏りすぎて「価値」を軽視して、これらに拘りすぎると本末転倒となるのではないだろうか。
現場の多くの介護スタッフ等は、要介護者の「生活観」「意思」「思い入れ」「感情」などを基本に介護サービスを考えている。むしろ、そこに「やりがい」を見出している。
しかし、データに偏る介護方針になってしまうと、本来の「介護」の意味が軽視され、「生活」重視ではなく、より「医療」といった側面が強い介護に陥る危険性がある。
6.介護経営者の責務
介護保険制度が始まって21年が過ぎたが、「科学的介護」は画期的な出来事であろう。しかし、考え方によれば「生活」モデルよりも「医療」モデルに偏ってしまう介護保険制度となる危険性もはらんでいる。もちろん、「介護」は医療的側面も重要ではあるが、「生活」主体のサービスである。
介護経営者は、データ管理に陥る危険性を認識し、介護現場スタッフ等と話し合いを重ね、「科学的介護」のより良い活用を模索していくべきであろう。そうしなければ、現場と経営者が乖離してしまい、介護スタッフ等のモイベーションが下がってしまう。