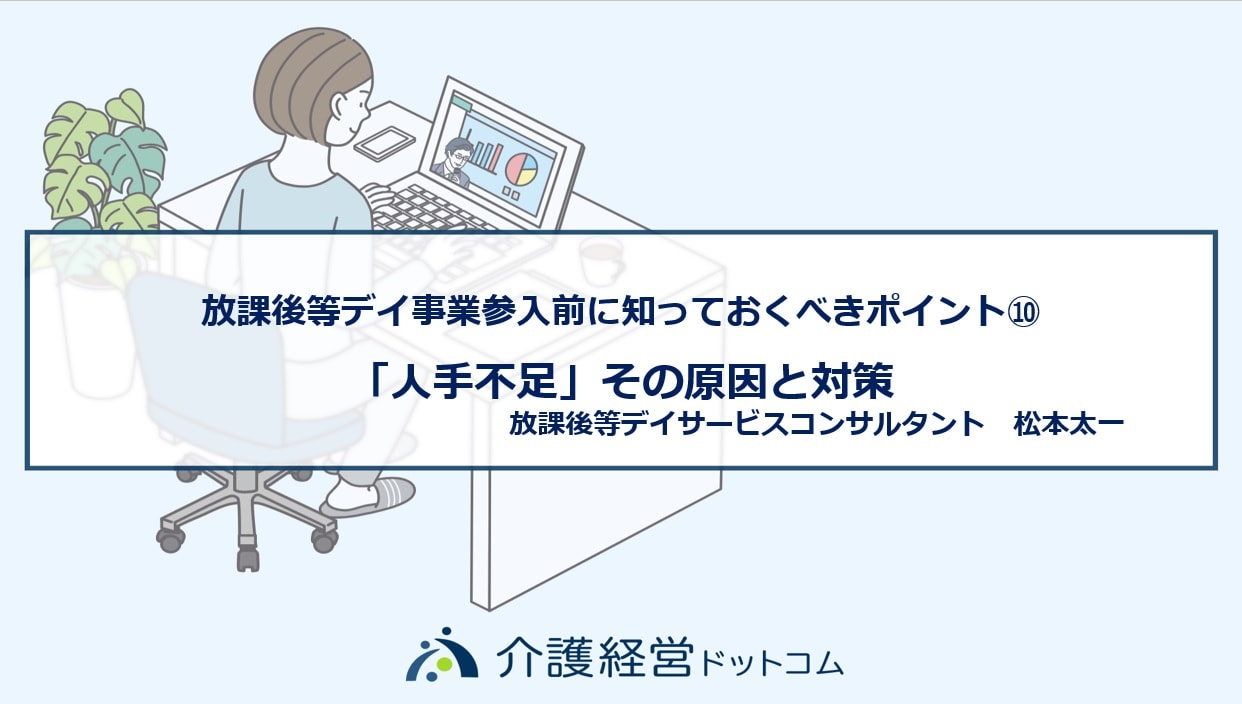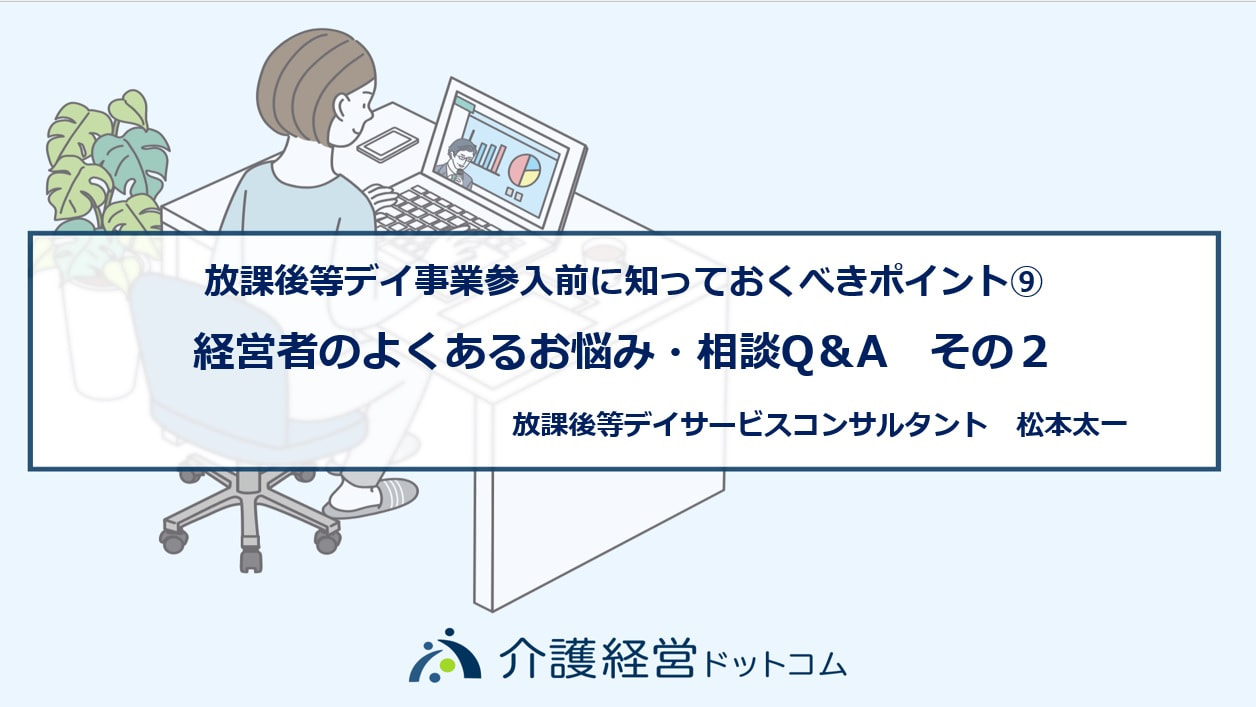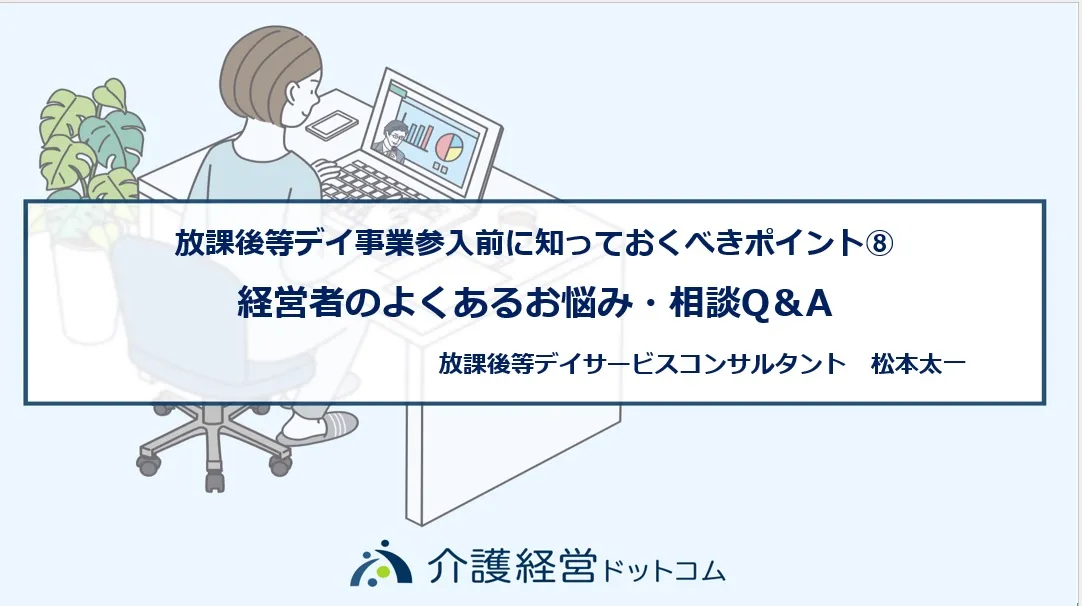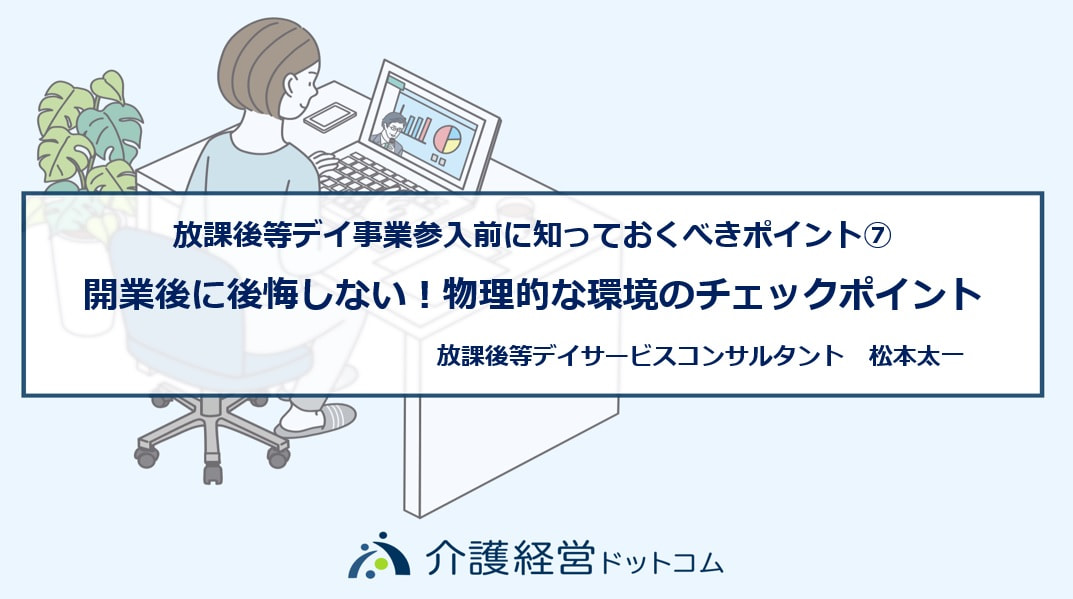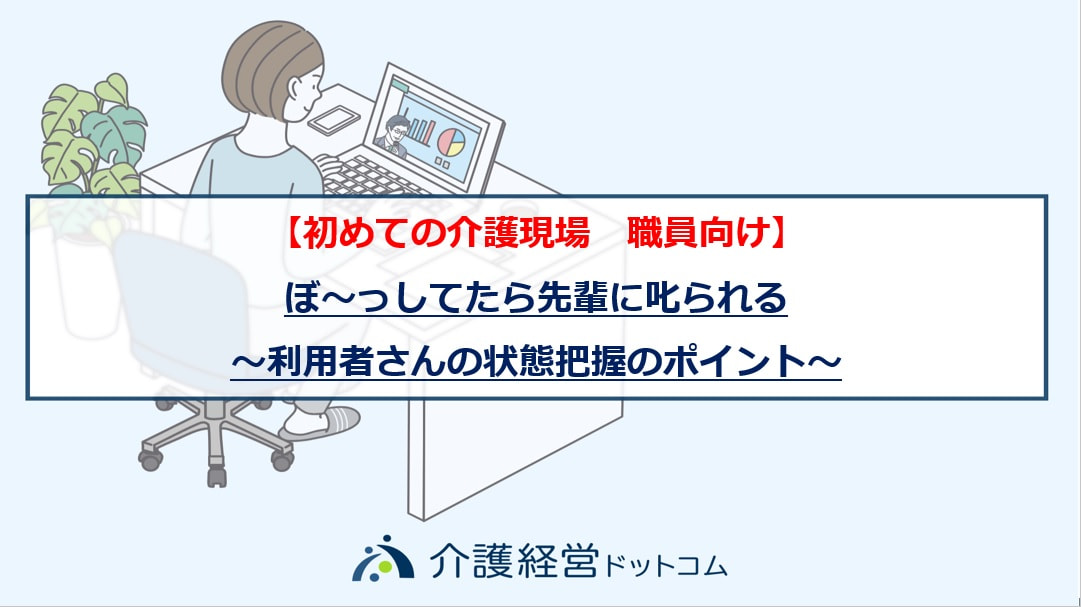1.カスハラには「チーム」で対応
特別養護老人ホーム内のデイサービスで以下のカスハラ事例が発生したとします。
80歳の女性利用者が、デイサービスを利用中、職員の目前で、膝をつくようにして転倒しました。
その際、職員はすぐに利用者の状態を確認しましたが、大した転倒ではなく、負傷も見受けられなかったため、ご家族への報告をうっかり忘れてしまいました。
利用者の帰宅後、ご家族が利用者の膝に内出血を発見します。ご家族が利用者に事情を聞いたところ、利用者は「デイサービスで転倒した」と答えます。転倒の事実を知らされていなかったご家族は烈火のごとく怒り、施設に電話してきました。
「利用者が施設で転倒したと言っているが、そんな報告無かったじゃないか!どういうことだ!」
施設職員は、転倒の事実をきちんと報告していなかったことについて謝罪しますが、ご家族の怒りは収まりません。翌日、ご家族が突然、施設に乗り込んできて、事務室で大騒ぎします。「昨日、転倒事故があったとき、近くにいた職員を全員呼んでこい!」「一体どういう教育をしているんだ!全員に謝罪させろ!」「今日の夜にもう一度来るから、それまでに関与した職員を集めておけ!」などと怒鳴り、居合わせた職員は怯えてしまいました。
そして、その夜、転倒事故の際に居合わせた職員をできるだけ集め、ご家族と面談しました。この面談でもご家族の怒りは収まりません。職員を「お前」呼ばわりし、頭ごなしに否定するといったようなひどい状況になりました。「お前は馬鹿か!」といったような侮辱的は発言もありました。
それだけでは収まらず、後日、事業所にFAXで「無責任な対応をしたことについてどのように向き合うのかを文書で回答せよ」「もし仮に、大きな後遺症が生じた場合、どう責任を取るつもりだ」という内容の文書が大量に届きます。施設側は、どう対応して良いか分からず、いつまで続くか見通しのつかない状況に疲弊しています。
このケースは、弁護士法人かなめが実際に対応した複数のカスハラ事例を元に設定しました。現実に起こり得る事例です。このようなカスハラ事例に対してどのように対処していけば良いのでしょうか。
まず、結論から申し上げると、このご家族の言動は法的に問題のある行動です。職員を長時間繰り返し拘束したり、大量の文書を送りつけるなど、具体的に事業所の業務を妨害していると評価できます。場合によっては、強要罪(刑法第223条)、侮辱罪(刑法第231条)、威力業務妨害罪(刑法第234条)が成立します。このような事態に対しては、必ず「チーム」で対応するようにして下さい。つまり、「職員を1人で対応させない」「管理者に任せっぱなしにしない」ということです。
誰にとってもクレーム対応は辛い作業です。できれば避けたいことでしょう。しかし、ケースにあるような事態の対処を組織ごととして捉えず、「管理者だから」とか「その場に居合わせた職員だから」といった理由で放置してしまうと、対応している職員は精神的に追い詰められてしまいます。以下の図にも表れているように、悪質クレーマーは「現場」の職員を攻撃する傾向が高いです。現場で対応する職員は、必ず2人以上のチームを組むようにしましょう。つまり、クレーマーが事業所に乗り込んできた時は1人では対応せず、2人以上で対応する、ということです。
自宅に訪問する際も、決して1人で訪問してはいけません。少なくとも2人で訪問するようにしましょう。そして、役割分担して下さい。1人は「聞き役」、もう1人は「記録係」です。これだけでも悪質クレーマーに与える印象は異なります。「この法人は組織対応をしているな」「きちんとクレーム対応に関する教育がなされているな」と内心手強さを感じるはずです。
ケースに照らして解説すると、「転倒事故に居合わせた職員を全員集めろ」というような要求には応じる必要はありません。何よりそのような法的な義務はありませんし、仮に職員全員を集めると現場の業務を中断せざるを得なくなるでしょう。出勤時間を終えて帰宅している職員もいれば、シフト等で同日不在の職員もいるはずです。
転倒事故が発生した際に行うべきことは、事実関係の整理と関係者への報告、法的に問題がある場合であれば、生じた結果に対して必要な範囲での賠償、再発防止策の構築です。全職員が謝罪する、ということは、法的にも道義的にも不要です。
たしかに、介護事業所側に何らかの落ち度がある場合、利用者のご家族が怒りにかられる気持ちは理解できます。大切なご家族に関することですから、感情的になることは人として当然であり、介護事業所側としても、真摯な謝罪が必要な場面はあるでしょう。しかし、だからと言って、職員を頭ごなしに怒鳴りつけたり、事業所に大量のFAXを送ったり、「お前」「馬鹿」などと面前で言い放つことは非常識な行為と言わざるを得ません。人を不当に傷つけている時点で、少なくとも「不法行為」でしょう。
過去に、「大韓航空ナッツ・リターン事件」というカスハラ事件がありました。大韓航空の副社長が乗客として乗車していたのですが、CAのナッツの提供方法に憤慨し、他の乗客のいる面前でそのCAを怒鳴り付け、果てには搭乗ゲートへ引き返すよう機長に指示し、出発が約20分も遅れてしまった、という破天荒な事件です。メディアが取り上げたことで世界的に有名になった事件ですが、後に副社長は逮捕されるという事態に発展しました。
どんなに立場のある人であったとしても、誰かを傷つけるような言動をすることが正当化されるわけではないのです。

2.秘密録音は違法?
ケースのような違法な言動をする悪質クレーマーに対しては、現場はチームで対応した上で、図のとおり、対応窓口である上司に相談し組織対応を検討していきます。ケースの事例では、刑法犯罪に該当する可能性のある言動があるため、法的な対応をしていく必要があります。
ここでの法的な対応とは、警察への協力要請、顧問弁護士への相談、悪質クレーマーへの警告文の送付、利用契約の解除です。この際、重要になってくるのは「証拠」です。つまり、警察への協力要請をする際も弁護士に相談する際も、具体的に悪質クレーマーがどのような言動に及んでいるのかを伝える必要があります。ただ単に「事業所に乗り込んできて罵倒された」と伝えるだけでは、警察も弁護士も中々動くことができません。そこで必要となってくる証拠は「録音データ」です。
では録音をとるために相手の了解を得る必要はあるのでしょうか。
結論からいうと、このような悪質クレーマーへの対応の際には、その言動をこっそり秘密で録音することは法的に問題ありません。むしろ、相手に対して、「今から録音をとりますね」と伝えると、余計に相手が激昂してしまう可能性が高く得策ではありません(敢えて録音をとると伝えて相手を牽制する場面もありますが、ここでは論じません)。
3つの観点から、悪質クレーマーへの対応場面において秘密録音が許される理由を解説します。
まず、悪質クレーマーは「秘密録音はプライバシー権侵害だ!」と主張することが考えられますが、悪質クレーマーへの対応場面において、秘密録音がプライバシー権を侵害することはありません。プライバシー権とはみだりに私生活に侵入されない権利です。対外的にクレームを伝えている以上、プライバシー性は低いですし、そのようなクレーマーの利益よりも、クレーマーに正しく対処するためにクレーマーの言い分を正確に記録するという企業防衛の利益の方が重要です。この理由から、クレーム内容を正確に把握するために行われる秘密録音はプライバシー権侵害にはなりません。
次に、悪質クレーマーは、秘密録音が個人情報保護法に違反していると主張することが考えられますが、悪質クレーマーへの対応場面において、秘密録音が個人情報保護法に違反することはありません。悪質なクレーマーとの会話を録音する行為は、「通知等によって、業務妨害行為を行う悪質者情報等を本人から取得したことが明らかになることにより、当該情報を取得した企業に害が及ぶ場合」に該当すると考えられるため、個人情報の利用目的の通知も公表も不要と考えられます(個人情報保護法第18条4項2号)。
また、悪質クレーマーと言えるか微妙なケースであったとしても、顧客から寄せられるクレーム内容を録音する目的は、「顧客からのクレームに適切に対応するため」にあたります。つまり、「取得状況からみて利用目的が明らか」(個人情報保護法第18条4項4号)と考えられるため、個人情報保護法に抵触することにはならないと考えます。
さらに、このような秘密録音は民事事件の証拠として有効に採用されますし、刑事事件の証拠としても有効に活用できます。もっとも、例えば、秘密録音をとるために、人の住居にこっそり侵入して盗聴器を仕掛けるなどの行為は犯罪に該当しますから、そのような悪質な手段で秘密録音をすることはご法度です。証拠としても認められなくなるので注意しましょう。
3.現場職員・管理者・警察・弁護士との連携
図にある通り、現場職員はチームを組んでカスハラに対応し、必ず対応窓口である管理者等のマネジメント層の職員に判断を仰いで下さい。ここで筆者が非常に重要だと考えているのは、対応窓口を務める管理者等のマネジメント層の職員が、すぐに顧問弁護士に相談できる環境が整備されているか、という点です。
現場職員だけでは判断が難しいからこそ、社内に対応窓口を設置し、そのポジションを管理者等のマネジメント層が担当する訳ですが、カスハラは法的な判断を求められることが非常に多く、法律実務の教育を受けたことのない管理者にとっても、その対応は非常に荷が重い業務です。従って、その対応窓口を支える仕組みが必要なのです。
対応窓口を支える仕組みとは、すなわち、顧問弁護士の存在です。ケースの事例のような状況が生じると、現場は「今すぐ相談したい!」と思います。このような状況ですぐに相談できるチャット窓口が弁護士との間で開設されているかどうかがとても重要です。
今の介護現場では、マネジメント層を速やかにサポートできる顧問弁護士の体制が十分ではありません。顧問弁護士はいるものの、施設長や管理者がその弁護士に直接アクセスする方法がないという状況は、筆者自身が全国の介護事業所の職員から幾度となく聞いてきた「現場の声」でした。どこでもオンラインに接続している状況が常識になったデジタル社会の現代において、弁護士と「常時接続」できる環境があるかどうか、を今一度皆様の組織でも見直して下さい。
顧問弁護士は、警察への相談の仕方のアドバイスをする他、録音データに基づき、クレーマーの言動が違法なレベルに及んでいると判断した場合には、警告文の起案等、速やかに法的サポートを行います。このような法的サポート体制があると、対応窓口を務めるマネジメント層の職員は心理的に安心し、精神的負荷が軽減されます。
4.カスハラ対応ができる契約書になっている?
悪質クレーマーの言動が苛烈に過ぎることから、利用契約を解除する場面があります。その際、皆様は利用契約書を見て、契約解除の手続きを行うことになります。
しかし、多くの利用契約書は、解除条項が以下のように定められており、対応に苦慮することがあります。
事業者は、利用者が故意に法令違反その他著しく常識を逸脱する行為をなし、事業者の再三の申し入れにもかかわらず改善の見込みがなく、本契約の目的を達することが著しく困難となったときは、文書により、2週間以上の予告期間をもって、この契約を解除することができる
よく見かける条項だと思います。この条項のどこに問題があるのでしょうか。
それは、冒頭の「利用者が」という部分です。実際、多くのカスハラ案件では、利用者に問題があるというよりは、そのご家族や関係者等が主体になることが多いのです。そうすると、細かな部分まで指摘してくる相手の場合、「契約書には『利用者』としか書いていないじゃないか!俺はその家族だから『利用者』には当たらないだろう!」といったように難癖をつけてくる可能性があります。
仮に上記のような条項であったとしても、民法のルールに基づくと契約の解除自体は可能なのですが、このような揚げ足取りに近いクレームに対応するのは時間の無駄です。従って、「利用者が」という部分を「利用者またはその身元引受人ないしご家族、その他関係者が」というように主体を拡張しておきましょう。その他にも契約書には気を付けるべきポイントがありますから、介護業界の実態をよく理解している弁護士に契約書や重要事項説明書のリーガルチェックを依頼することをお勧めします。
5.HP、重要事項説明書で法人の「カスハラ、ダメ絶対!」を明示しよう!
最後に、組織対応として重要なのは、「組織の姿勢」です。
カスハラには厳しく対処する、という姿勢をしっかりとHPや重要事項説明書に示しておくことが大切です。職員がカスハラの被害に遭ったときのことを想像してみて下さい。管理者としてその事態に対応しなければいけません。
その際、カスハラの加害者と話をするときに、「重要事項説明書においても事前に説明させて頂いているとおり、当法人ではご家族の方の不当要求には毅然とした対応をする方針を示しております。」「ホームページにも記載があるとおり、働きやすい職場創りを重視しており、カスハラにはしっかりと対処させて頂く所存です。」といったように、事前に説明している状態を作出しておくことで、スムーズに対応することが可能になります。
介護事業とジャンルは異なりますが、チームのコラボレーションを促進し、「働くを楽しくする」というコンセプトで「Backlog」「Cacoo」「Typetalk」といったツールを開発提供している株式会社ヌーラボという会社があります。この会社は、2020年6月15日にカスハラへの対応に関する方針を同社のホームページ上にアップしています。企業としての姿勢を示す、という点で非常に参考になると思います。URLを掲載しておきますので、皆様も是非チェックして下さい。