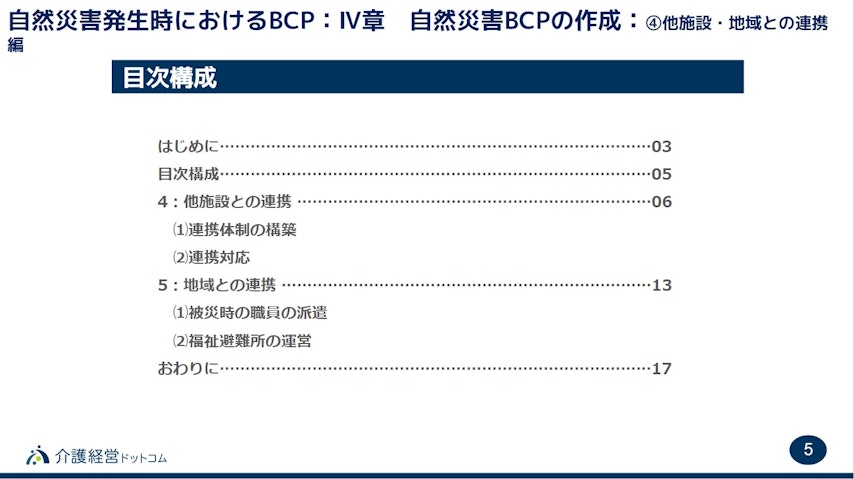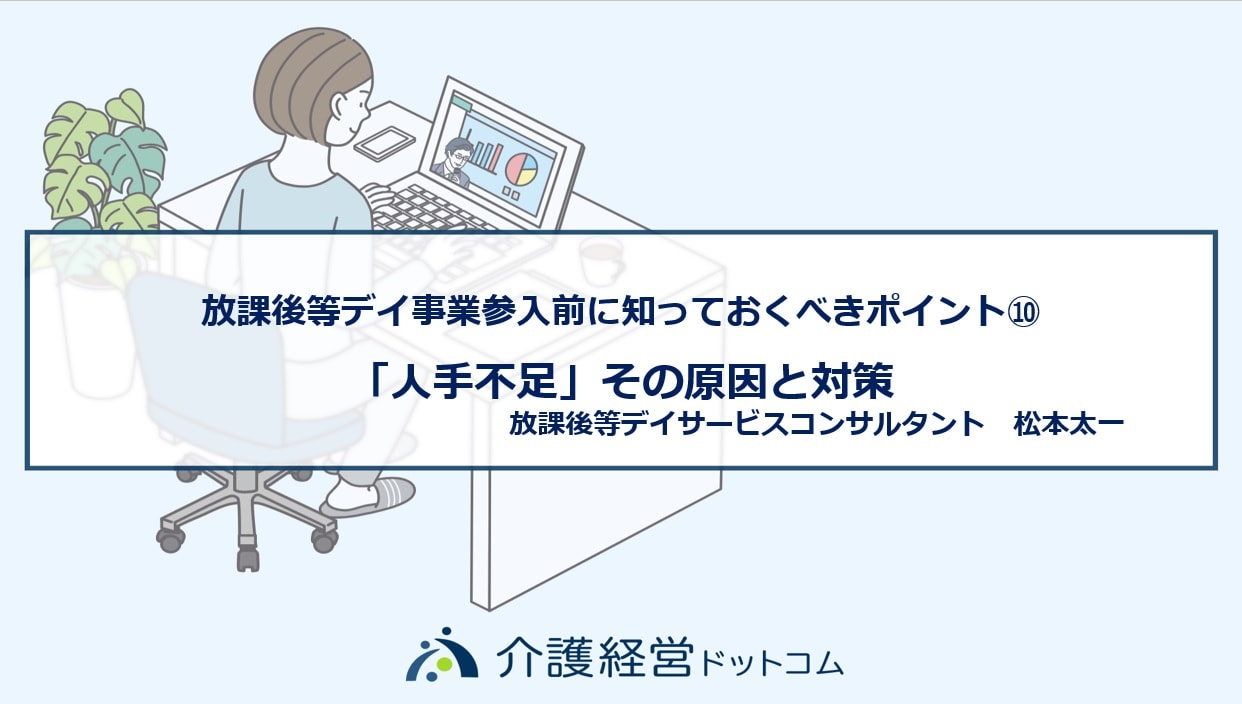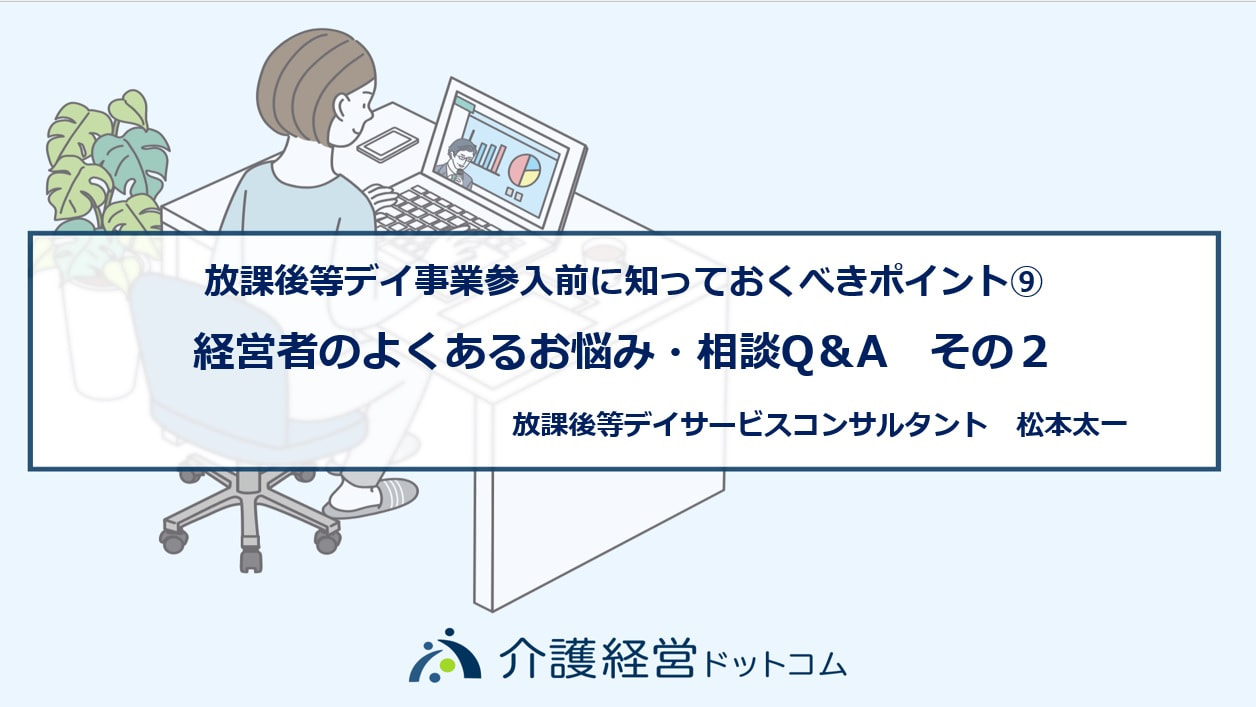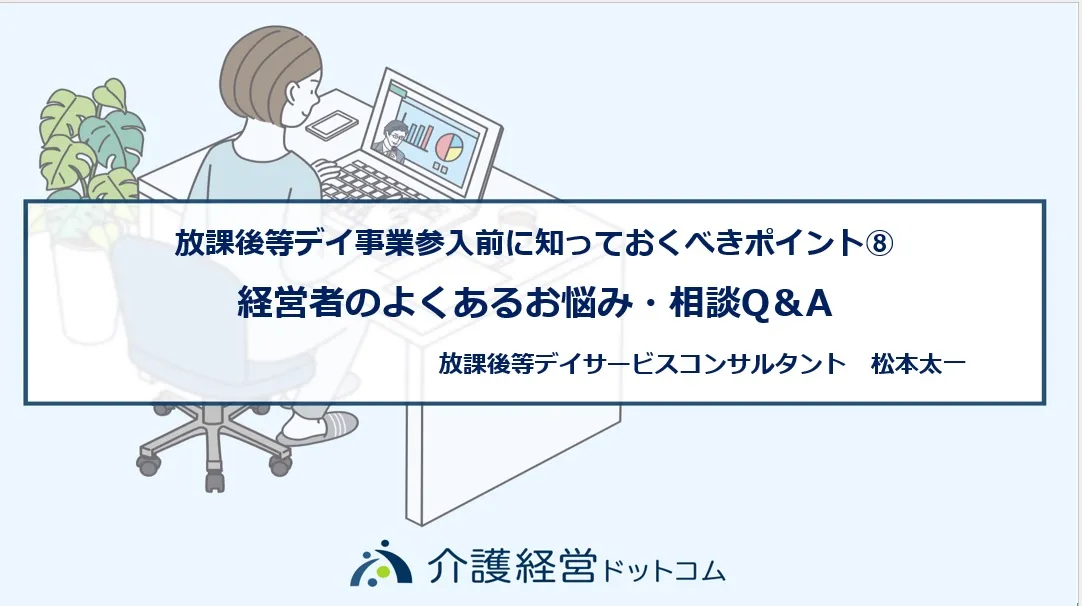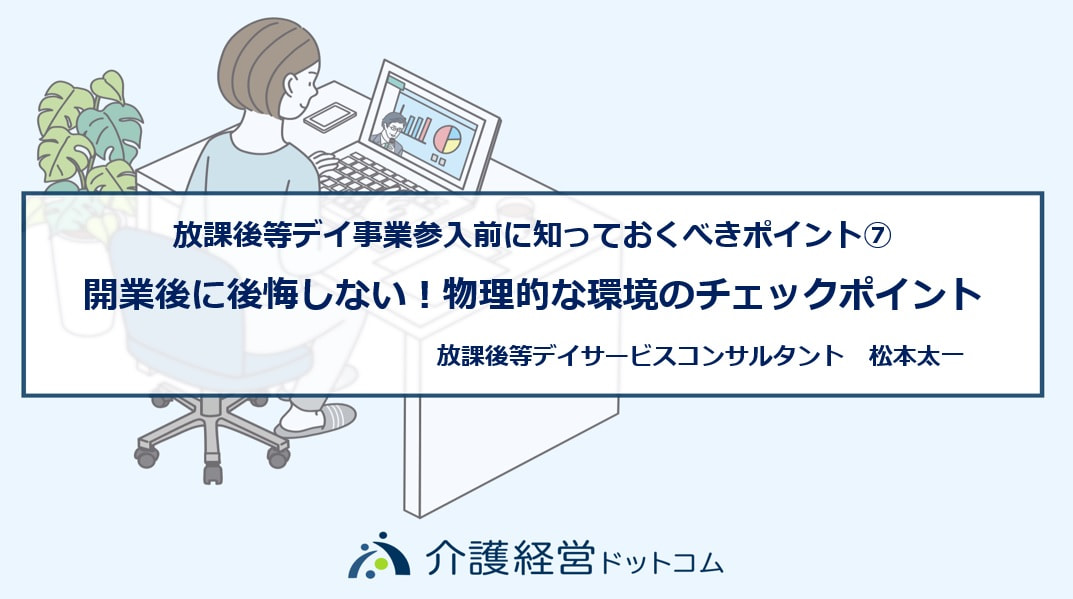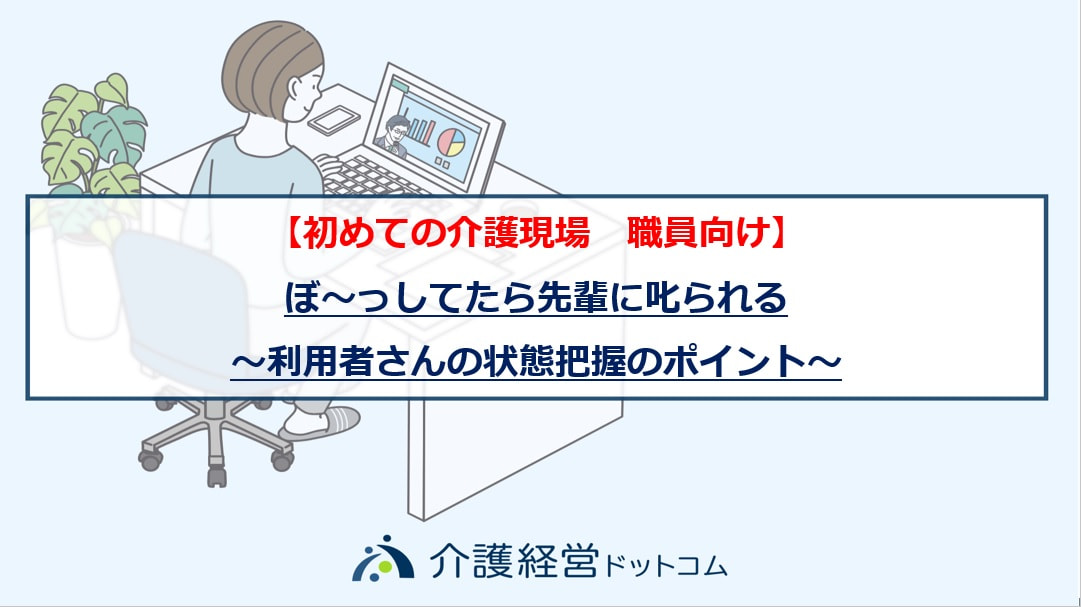人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関する理解
本人の尊厳を追求して自分らしく生きてより良い最期を迎えるためには、人生の最終段階における医療・ケアをどうするべきかということが重要になります。この医療・ケアを適切なものとするには、どういった形でプランニングすればよいものになるのかを明確にするという観点から作成されたガイドラインです。
近年の高齢化や地域包括ケアシステムの構築が進む中で諸外国でも普及してきているアドバンス・ケア・プランニングという概念を取り込みながらガイドラインも改定されてきています。
現時点では本人、家族と医療従事者、介護従事者が最善となる医療・ケアを作り上げようとしたときに、どうすればよいかというプロセスを示すものになっています。本人が希望する最期の迎え方は日々変化します。
そのため、このガイドラインに沿って本人、家族と医療ケアチームで日ごろから話し合いを重ねていくことが重要になります。またこのガイドラインに沿って話し合ったことは、その都度文書にまとめておくことが必要です。
基本的な考え方
人生の最終段階を迎えた本人家族と医療・介護従事者が最善の医療介護サービスを作るためのプロセスを示すものです。
本人の希望する医療介護サービスを提供することを第一に考えます。医療介護サービスの提供に際しては本人の意思決定(インフォームド・コンセント)が大切です。
しかし状態によっては本人の決定した意志を確認することが困難となったり、本人の意思はつねに変わり続けることが考えられることから、本人のみではなく、家族や信頼できる人などを含めて話し合いは続けられることが求められます。万一本人の意思が確認できなくなったときには、それまでの本人の人生観や価値観、どのような生き方を望むのかを含めてできる限りの把握に努める体制を準備しておくことが必要です。話し合いの中で合意形成ができない場合には、外部の専門家などの話し合いの場を設け、その助言を貰いながら医療介護方針を見直し合意形成することが求められます。
これらのプロセスによって話し合った内容や合意した内容については、その都度文書にまとめておくことが必要です。
アドバンスケアプランニングとは
人生の最終段階において本人の大切にしていることや望み、医療介護サービスにどのようなことをのぞんでいるかを明確にするため、本人自身や家族などの本人が信頼する人を交えて、医療介護サービス従事者と話し合うことをアドバンスケアプランニングといいます。
万一命の危険が迫った場合、約4分の3の人は自分の意志を伝えることができなくなるといわれています。そのような時でも、あらかじめ本人の意志が周囲に知らせされていれば、意思どおりの治療や介護の方針に沿ってサービス提供することができます。大切な人生の最終段階において、本人の希望するサービス提供をするために必要となるのがアドバンスケアプランニングです。
同時に本人の意志を代弁することを求められることになった周囲の人の心理的負担を減らすこともできます。
ではどのようにアドバンスケアプランニングを進めれば良いのでしょうか。
まずは本人の意志を確認することから始めます。自身が最期に向けて大切にしたいことを明確にします。確認するべきことは多岐にわたりますが、少しでも長く生きたいのか、状況によっては積極的な延命は望まないか、といったことから始まり、どのような介護を受けたいか、経済的にはどのような方針で介護してほしいか、万一自分の意志が伝えられない状況になったときは誰に自分の意志を代弁してほしいか、などの項目を話し合いのなかで確認していきます。
これらの項目を確認していく中で本人や家族などだけでは決定できないことも考えられます。そのような時には本人にサービス提供する側の医療、介護従業者の意見を聞けるよう、医療介護従事者も話し合いに同席することが求められます。これらの話し合いは一回話し合って方針が決まったらよいというものではありません。本人の体調、心理状況や病状の進行によって本人の希望する内容というものは常に変化するものです。本人の状況に変化があったと考えられるときには周囲が積極的に改めてアドバンスケアプランニングを行うことで、その時により適したプランになっていきます。
アドバンスケアプランニングのことを人生会議ということもあります。人生の最終段階をより良いものとするための会議です。必要に応じて何度も話し合うようにします。
人生の最終段階における医療・ケアの在り方
最も大切となるものは本人の意思決定を基本とした医療ケアの提供です。本人の意思決定を適切なものとするため医療ケアを提供する側からの適切な情報提供と説明が欠かせません。状況変化があれば本人の意思も変わることが考えられますので、繰り返し本人の意思決定内容を確認する話し合いが求められます。これらの話し合いには本人が病状の進行とともに決定した意思を伝えられなくなることも考えられることから家族などの信頼する人を交えて行うことも必要です。
次に考えるのは、医療ケア行為の開始や不開始、医療ケア内容の変更や中止については医療ケアチームによって医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断するべきであるという点です。確認しておいた本人の意思に沿う形で医療ケア行為を提供しますが、本人の予後がどの程度の期間になるのかや、急性増悪の発生などにより具体的な医療ケア行為の内容は異なってきます。
具体的な内容については本人の意思に沿う形で医療ケアチームにより適切なものとなるように判断されなければなりません。もちろん緊急時には生命の尊厳を尊重して医師が医学的妥当性と適切性に基づき判断せざるを得ませんが、その後は医療ケアチームでの検討によって、これらの判断がされることが求められます。
もう一つ、医療ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和して、本人や家族などの精神的、社会的な援助も含めた総合的な医療ケアを行うことが求められています。安心、快適な人生の最期を迎えるにあたっては痛みを含めた不快感を取り除くことは絶対に必要なことです。
本人にとって十分に不快感の緩和ができていない状況では、人生の最終段階を安心快適に過ごすことができません。それに加えて本人が不快感に苦しんでいる状況をみる家族にとっても負担が大きなものになります。加えて疼痛緩和などの緩和ケアを行う段階に至っては、本人の最期が近くなっていることも含めて精神的、社会的にも問題や不安を抱えていることが多くなります。可能であれば、これらの問題や不安に対応できる人やケアに関わる介護支援専門員などがチームに参加することで、より良い緩和ケアとすることが望まれます。
参考:「アドバンス・ケア・プランニングいのちの終わりについて話し合いを始める」
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000173561.pdf
「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン解説編」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000197722.pdf
「これからの治療・ケアに関する話し合い」
https://www.med.kobe-u.ac.jp/jinsei/acp_kobe-u/acp_kobe-u/doc/EOL_shimin_A4_text_201909.pdf