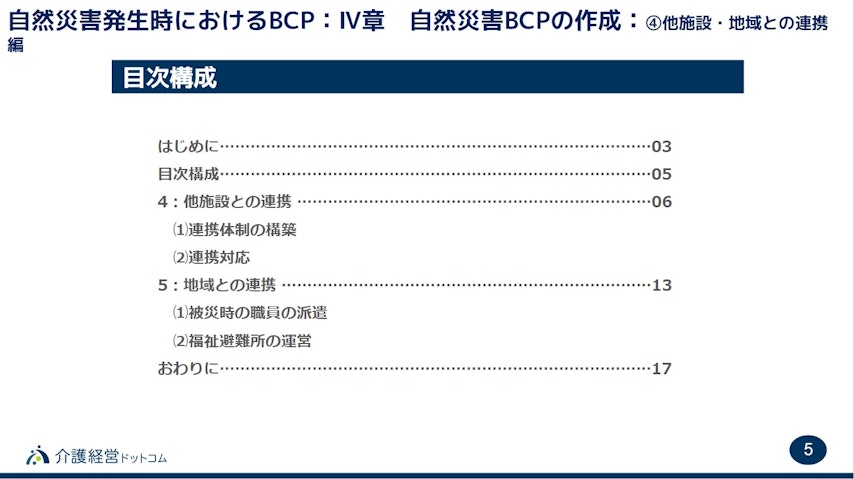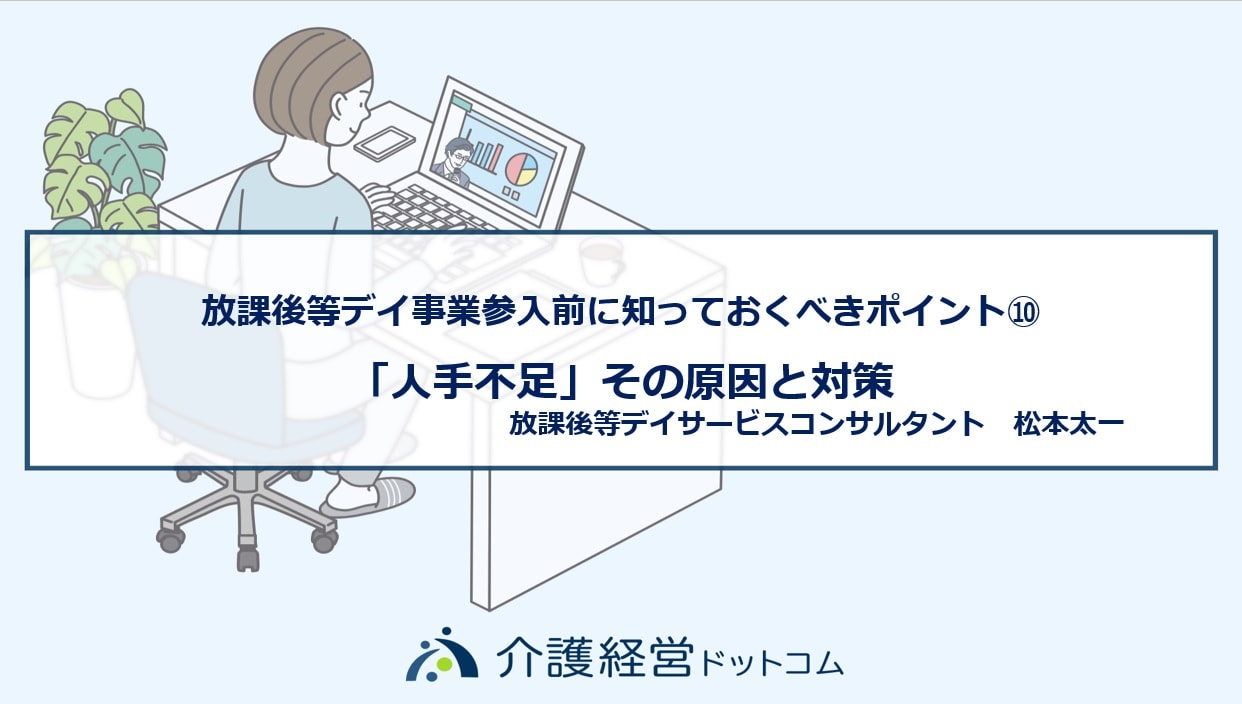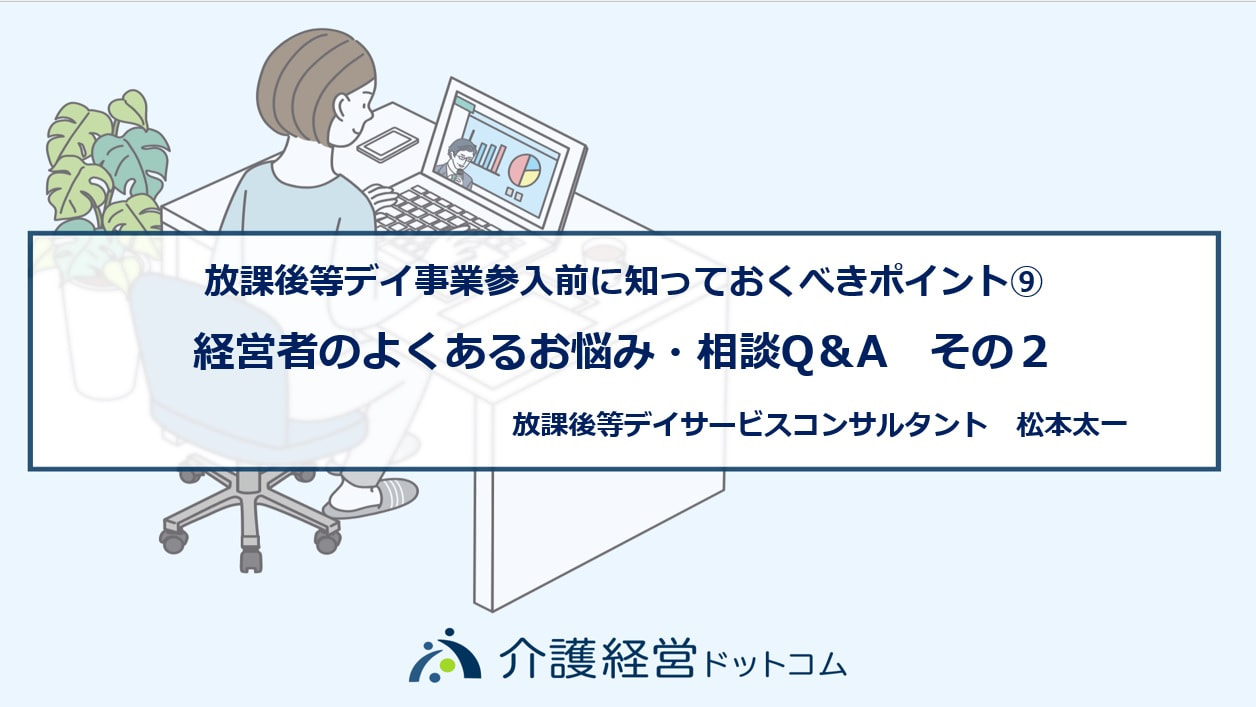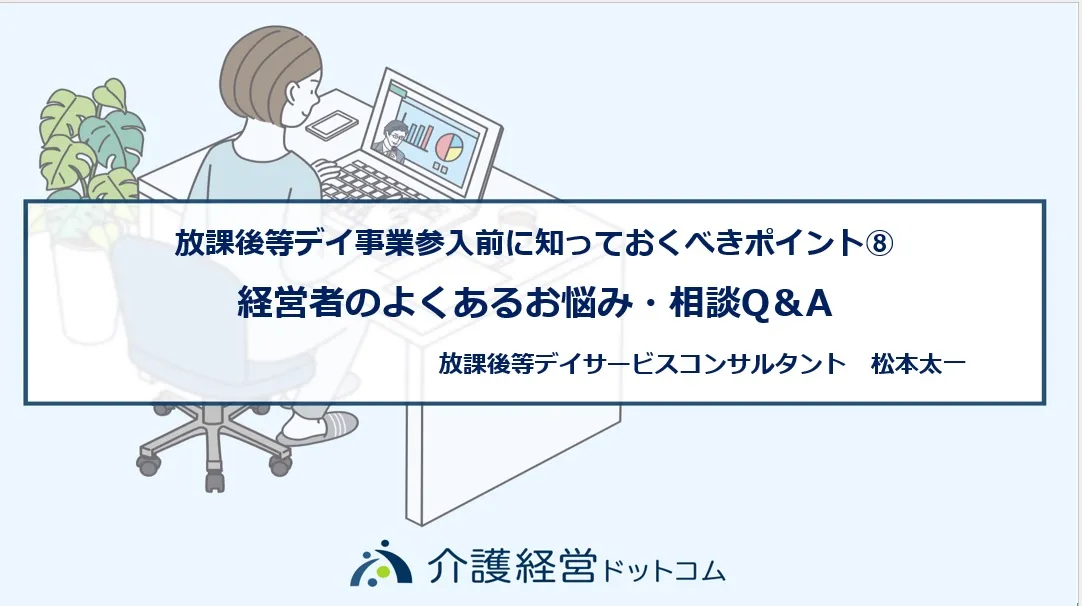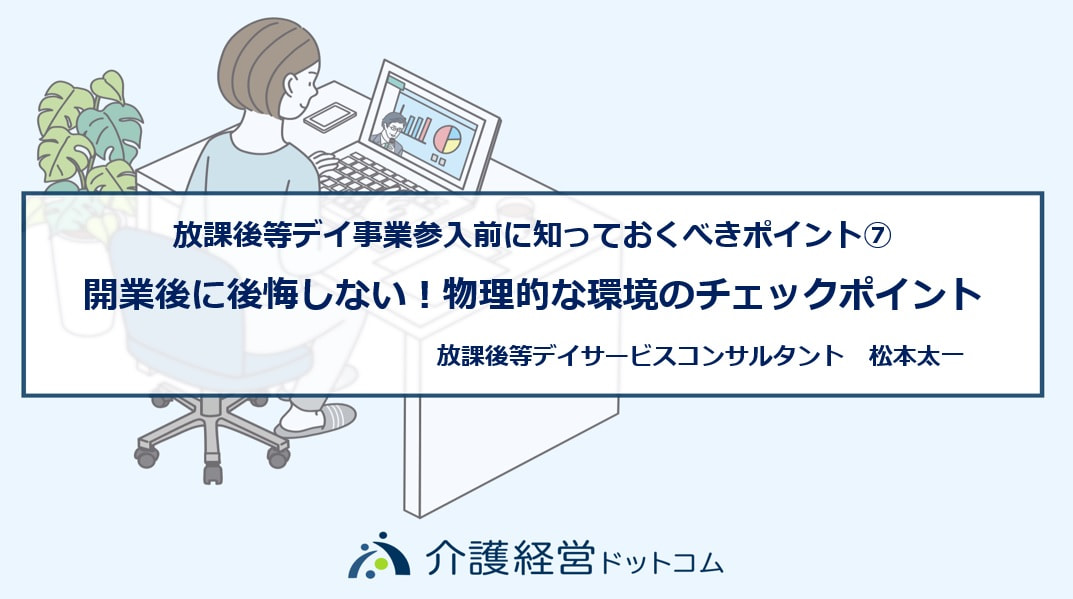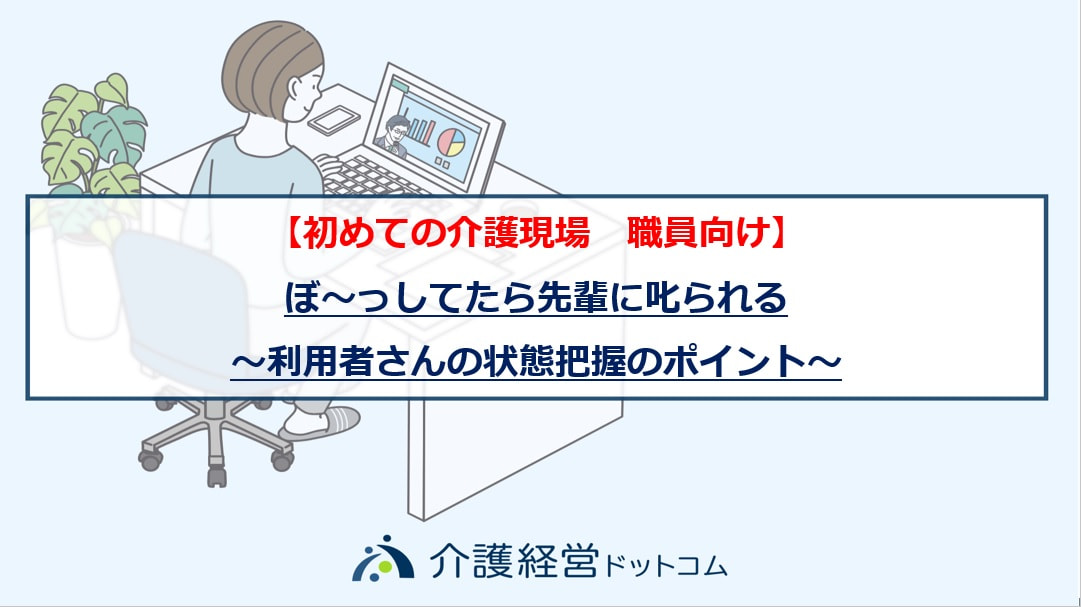認知症の定義
認知症とは、様々な原因で脳の細胞が死ぬことで脳全体の働きが悪くなり、いろいろな障害が出ることで生活上の支障がある状態がおおよそ6カ月以上続いていること、と定義されています。認知症の原因となるものとして最も多いものは、脳の神経細胞が時間をかけてゆっくりと死んでいく「変性疾患」となっています。代表的な病名は、アルツハイマー病、前頭・側頭型認知症、レビー小体型認知症などが挙げられます。次に多いものは脳梗塞、脳出血、脳動脈硬化などが原因となり、神経細胞に栄養や酸素が行き渡らなくなることで部分的に神経細胞が死んでしまう「脳血管性認知症」です。
これらの疾患を原因として発症する認知症は加齢による物忘れとは異なります。加齢による物忘れは、体験の一部だけを忘れてしまうもので、日常生活を送るうえで支障とはなりませんが、認知症による物忘れは、体験全体が抜け落ちる形で忘れてしまいます。そのため日常生活を送るうえで大きな支障となります。
中核症状
認知症になってしまうことで現れる症状には大きく分けて2つあります。認知症になった場合程度の差はあれども必ず現れる中核症状と言われるものと、人によって現れ方が異なる周辺症状と呼ばれるものの2つです。中核症状はうまくものを覚えられない「記憶の障害」、考えがまとまらない「思考の障害」、目の前のもが何かわからない「理解の障害」、どうしたらよいかわからない「判断の障害」が現れることで日常生活に支障が生じます。
具体的には5つの症状があり、時間・場所・人物などの見当がつけられなくなる「見当識障害」、言葉を見つけ出す、理解する、話が理解できなくなるなどの「失語・言語障害」、運動機能は充分にあるにも関わらず、衣服の着脱や使い慣れた道具を使うなどの動作ができなくなる「失行」、視力能力は充分にあるにも関わらず見ている空間を認識できなかったり、普段使用しているものを見てもそれが何なのかわからなかったり、自分の体の部分の認知ができなくなったりする「失認」、料理を作る段取りがわからなくなったり、服を着る順番がわからなくなったり、排泄時の一連の動作がわからなくなったりする「実行機能障害(進行機能障害)」があります。
周辺症状(行動、心理状態)BPSD
周辺症状とは、行動・心理症状(BPSD)とも呼ばれます。中核症状と本人の性格や環境の影響によっておこる症状を指します。性格や環境の影響によるものであるため、症状は多岐に渡りますが、主だった症状として代表的なものを紹介します。
1.人格・性格変化
認知症の初期ではあまり目立たないことが多いですが、症状の進行と共に変化が現れます。それまでの性格が強調されて現れることがある一方、それまでは非常に神経質だった人が大ざっぱになっていくなど、逆の性格傾向となることもあります。症状が進行していくと人格の解体が進み、名前を呼ばれても反応しなくなる状態になることがあります。
2.心理症状
アルツハイマー型認知症の初期段階では、記憶障害や自身の能力減退による不安や焦燥を生じることがよくあります。この心理症状が原因となり興奮やうつ状態になることがあります。場合によっては興奮やうつ状態が暴力行為や破壊行為、自殺企図となって現れることもあります。これらの衝動行為以外にも、昼夜逆転による不眠、身体症状の訴えになって現れることもあります。いずれの症状も認知症が進行するとともに軽減していき、精神的に安定した状態になることもあります。認知症の進行が相当に進んでいくと無為・自閉の傾向が強くなります。
3.幻覚・妄想
実際にはないものが見えたり聞こえたりする現象です。妄想とは訂正することが困難な誤った思い込みを指します。アルツハイマー認知症の女性によくある「物を盗られた」という妄想や、レビー小体型認知症によくある配偶者の不貞を確信してしまう「嫉妬妄想」、嫁がごはんを食べさせてくれないなどの訴えとなる「被害妄想」が代表的です。
4.徘徊
何の目的もなくうろつくことを指します。しかし徘徊している本人は目的を持っている場合が多く、徘徊を止めようとしても抵抗することがよくあります。認知症の初期段階から現れて進行とともに頻度も高くなります。徘徊することで運動量が多くなり体重減少につながったり、視空間認知に問題がある場合には転倒の危険性も高まります。
5.不穏・暴力行為
認知症の中核症状である記憶障害や認知障害により自分の思い通りに行動できなくなることに焦燥感や不安感を感じる状態の中、短気で怒りっぽい性格が先鋭化した場合には自分の行動を制限されたり、行動を強制されたりしたときに不穏になったり、暴力行為を行うことがあります。
6.過食・拒食・異食
適切な食事を摂る事を認識できなくなることで、一度に大量に食べたり、常に食べ続けたりする過食、食事することに無関心になり全く食べなくなる拒食、食べ物以外のものを食べようとする異食や、喉の渇きを認識しなくなり水を飲まなくなる飲水行動異常などが現れます。
7.失禁・不潔行為
ほとんどの失禁不潔行為は認知症の中核症状を原因として発生するため、認知症の進行とともに多くの人に見られるようになります。
8.睡眠障害
認知症がある程度進行した状態で現れることがあります。夜間の不眠、日中のうたた寝の繰り返しで睡眠と覚醒のリズムに障害を発生して昼夜逆転となる事もあります。
9.多動・寡動
認知症がある程度進行したときに多動傾向となることがあります。目的のない反復行為や一定の場所を徘徊するなどの行動として現れたり更に進行すると同じ話や言葉を繰り返すオルゴール症候群と言われる症状が現れることもあります。認知症の進行が進み末期には自発性の低下により、何もしない寡動状態となることがあります。
認知症の原因疾患
認知症は加齢による変化が主な原因です。代表的な疾患はアルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、血管性認知症などがあります。またこれらと比べると割合は少ないですがピック病(前頭側頭型認知症)も原因疾患として挙げられます。
1.アルツハイマー型認知症
脳神経細胞が障害された結果として細胞死が発生することが原因です。記憶の中枢である海馬を含めた前頭葉を中心として大脳が広範囲に障害されていくことで発生します。
2.血管性認知症
脳梗塞や脳内出血などの脳血管障害が原因となる脳細胞の死滅が原因となります。脳血管障害の後遺症として身体麻痺や機能麻痺が残る場合もあります。これらの麻痺は脳の障害された部位によって異なります。そのため血管性認知症は必ずしも記憶障害があるとは限りません。障害される部位によっては感情の変化が発生しやすくなることもあります。
3.レビー小体型認知症
脳細胞が死滅することが原因ですが脳細胞の死滅に加え脳細胞にレビー小体という物質が生じます。認知状態は変化しやすく幻視の出現やパーキンソン症状が現れることがレビー小体型認知症の特徴です。末期には振戦、筋固縮や無動となり機能が低下していきます。
4.ピック病(前頭側頭型認知症)
前頭や側頭葉の萎縮が原因です。50~60代で発症することが多くみられます。初期には記憶障害や見当識障害はほとんどなく、変化として典型的に現れるのは人格変化です。道徳観や倫理観が失われて意欲の低下が現れ、進行すると判断力や高度な知的機能が低下して失語に至ります。末期には精神荒廃が進み、無言、不潔症、歩行障害、失禁などが現れ寝たきりになります。
薬物療法・非薬物療法
薬物療法で使用される薬品は複数ありますが、大きく分けると次の4つになります。
1.抗不安薬
高齢者に使用すると過鎮静、運動失調、転倒、認知機能低下などのリスクが高いため、原則使用しません。
2.睡眠導入薬
服用後の半減期が長い薬もあり、持ち越し効果に注意が必要です。
3.抗うつ薬
転倒リスクが非常に高いと考えられていますので服用中は注意が必要です。
4.精神薬
歩行障害や嚥下障害などの副作用が考えられます。服用中の状態には注意が必要です。
いずれも、服用による副作用のリスクが高いため、主治医から本人あるいは家族に十分な説明をして服薬の同意を得ることが必要です。
また、認知症による心理・行動症状の対応は身体的、環境的要因であることが考えられることから第一義的に非薬物療法で行うことが必要です。
非薬物療法には代表的なものとして4つあります。
1.回想法
認知症により比較的最近の記憶が障害されても古い記憶は比較的残っていることがあります。手続き記憶も同様に残っていることが多いので、古い生活道具に触れながら本人の以前の生活や思い出話をしてもらうことで、本人の意欲が湧いてくる効果が期待できます。
2.リアリティーオリエンテーション
本人が今いる環境について、さりげなく、時間や場所などをわかり易くするように支援します。本人の気分を害しないため、しつこくならないように注意が必要です。
3.音楽療法
音楽に合わせて体を動かすなどしながら楽しい環境で過ごしてもらうなかでコミュニケーションを図ります。心も和む効果も期待できます。本人が心地よいと思える音量や雰囲気にも注意して環境を整えます。
4.アロマセラピーとタッチング
心地よい香りとタッチケアをすることで、オキシトシンやセロトニンが分泌されることでストレス軽減が期待できます。
ケアの基本姿勢
ケアの基本姿勢として重要なことをまとめると次の4点になります。これらを実践するときに重要なのは、認知症の方お一人お一人ごとに状況は異なるということです。認知症が原因なり、その方ごとに感じている不安や不快を軽減させたり取り除いたりすることを目的として取り組むことが重要になります。
1.総合的にアセスメントする
認知症の進行状態、日常生活行動全般の変化を観察し理解する必要があります。
アセスメントの項目は多岐にわたります。主だったところでいえば、コミュニケーション能力、食事、排泄、清潔、着替え、睡眠などの場面が挙げられます。
まず、これらの場面ごとに、更に細かくアセスメント(評価)すべき項目を挙げて日常生活行動の状態を把握します。
次に各場面ごとに期待する目標を設定します。この目標はアセスメントした項目のうち日常生活上の問題になるところが解消できるようなものにすることが望まれます。
目標が決まったら、この目標を達成するために必要なケアのポイントを設定します。
このとき、ケアのポイントと同時に、「してはいけないこと」も設定するようにします。
2.安心・安全な生活・療養環境をつくる
認知症の進行が進むと、ストレスなく許容できる環境から受ける刺激の量が少なくなる傾向があります。そのため環境からのストレスが行動・心理症状(BPSD)の原因となることがあります。過度な刺激を受けることがない環境で生活・療養していただくことが重要です。アセスメントして必要と考えられる環境整備をして安心・安全な環境を整備します。
3.認知症の行動・心理症状の要因を探る
認知機能が障害されることで身体状態や心理状態への影響が出やすくなります。このような状態になると、周囲の不適切な対応や不適切な環境などが原因となり、行動・心理症状が発生することもあります。現在行動・心理症状が発生しているのであれば、その発生原因が不適切な対応や環境にないかを確認することも必要になります。
4.チームでケアする
個人がどれだけ優れた知識や技術を持っていても、認知症の方を1人でケアすることはできません。前述のアセスメント、環境整備、ケア方法の設定などをしても、ケアに携わる人が異なる対応をしていては認知症の方にとっては良いケアになりません。認知症の方とその家族にとってなにが最善なのかを判断したうえで、チームでケアをしていくことが重要です。
認知症の人をケアする上での心構え
まず認知症は病気であることを理解することが大切です。そのうえで認知症の進行は原因となる病気や本人の身体状況、周囲の環境や介護のしかたなどによって大きな個人差があることを認識します。この特性を理解したうえでケアをする際に最も重要となるのは「認知症の人の尊厳を守る」ことです。どのようにしたら認知症の人の生活の質をなるべく長く維持できるかという視点でケアの方法を考えます。
具体的には、「おいしく食べること、飲むこと」「不快のない口腔状態を保つこと」「不快でない排泄をすること」「身体をきれいに保つこと」「安楽な姿勢で過ごすこと」「褥瘡などの新たな苦痛がないこと」などが挙げられます。
これらを実現するためには日常生活上しなければならないことがたくさんあります。認知症の人自身もすこしずつではありますが、自分が「できない」ということは感じています。ケアの基本として本人ができることは見守り、できないことをサポートするという気持ちを持つことが重要です。
ケアする側が間違った対応をすることで行動・心理症状を助長してしまいます。認知症の症状は個人差が大きいものですが、行動・心理症状を発症する前にはいつもと違うサインがありますので、普段の様子をよく観察して本人が安心快適な生活を送れるようケア方法や環境についても随時見直すようにすることも大切です。
訪問系サービスであれば、これら直接認知症の人に対するケア以外にも場合によっては家族に対する支援も考えます。
日常の介護をしている家族は介護の専門家ではありません。認知症に対する知識が足りず苦しんでいることや困っていることもよくあります。認知症の人の行動を理解できず疲弊したり適切なケアができなくなることにつながります。適切な知識があれば回避できるストレスを抱えてしまうこともよくあります。
「わからない」ことが多く、不安や苦しみを感じている認知症の人の気持ちを、日常の介護者となる家族の方に代弁者として伝えることが重要です。
このことで、家族はいままでわからなかった「なぜこんなことをする」「なぜそんなことをいう」などの答えを得ることができ、不安やストレスから解放されることもあります。家族が認知症の人を受け入れて、家族の関係性が円滑に維持できるような声かけや支援のタイミングを考えることも大切になります。
参考:「認知症ケアマニュアル」
http://www.osaka-kangokyokai.or.jp/CMS/data/img/2017_ninchishomanual.pdf